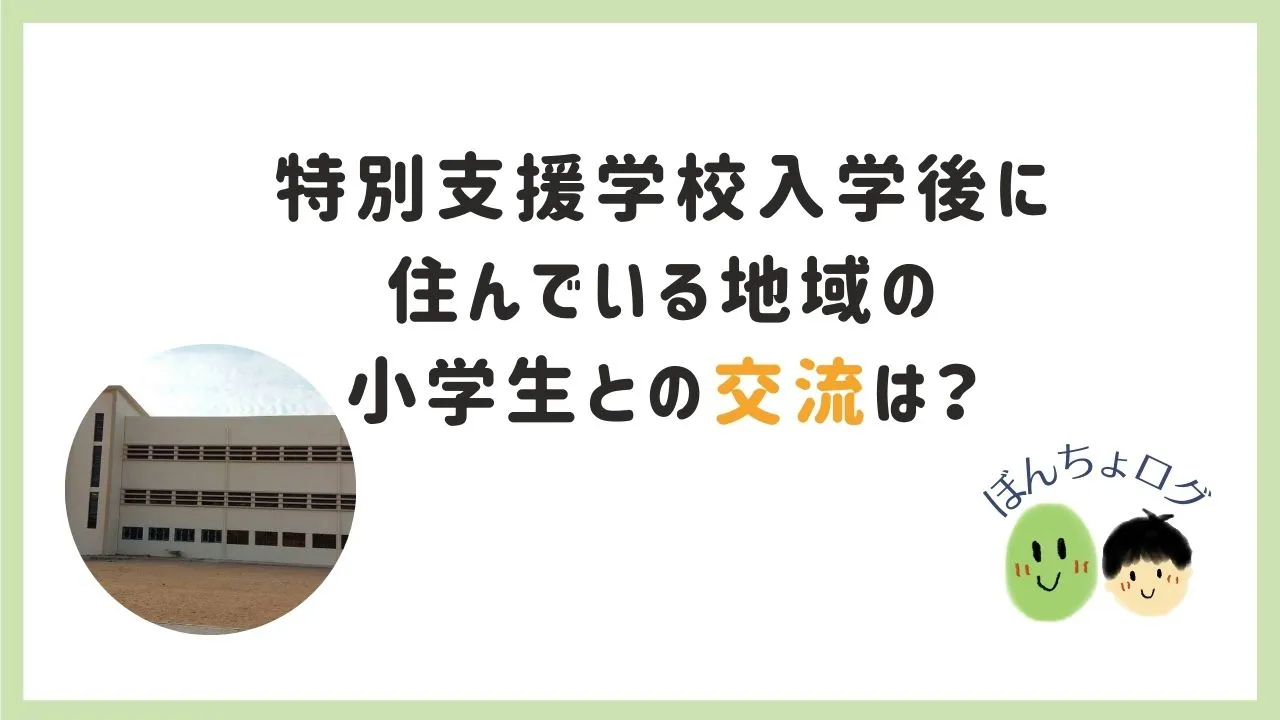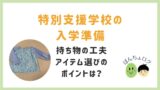特別支援学校に入学した後に住んでいる地域の小学生との交流があるかどうかは入学前に気になる人もいますよね。
ぼんちょも特別支援学校に入学後、住んでいる学区の小学校に訪問する機会(=居住地交流)がありました。
実際に地域の小学校で活動した実際の経験をもとに、特別支援学校に入学した子どもがどのように地域の小学校の子どもたちと交流しているか説明します。
小学校の子どもたちと一緒に活動できる居住地交流はどのように実施される?
- 次年度になる前に居住地交流を希望するかどうか尋ねられる
- 交流する学級や回数は選べる
- 保護者と支援学校の先生が同伴
子どもが住んでいる学区の小学校へ活動しに行くことを居住地交流と言います。
居住地交流がどのように実施されるのか説明します。
次年度になる前に居住地交流を希望するかどうか尋ねられる
ぼんちょの場合は、年度末に次年度の居住地交流を希望するかどうか支援学校の担任の先生から保護者に確認がありました。

ぼんちょさん、今年の居住地交流に行かれますか?

とりあえず1年生で初めてだし、行ってみます!

わかりました!では、ぼんちょさんが住む学区のA小学校に名前を登録しますね。
1年生の時は、入学前懇談の時に確認がありました。
どんな活動をするのかもわからなかったけれど「とりあえず経験!」と思い希望しました。
居住地交流を希望すると、学区の小学校に氏名が登録されるそうです。
2年生になる前にも確認があり、1年生の時の居住地交流を楽しめていたので希望しました。
交流する学級や回数は選べる

居住地交流では活動する学級を選べるんですけど、通常学級・知的特別支援学級・情緒特別支援級のうちどの学級で活動されますか?

(え!選べるんだ・・・!?)
知的特別支援学級でお願いします!
居住地交流の時に活動する学級は自由に選ぶことができました。
ぼんちょは知的特別支援学級を選びましたが、通常学級を選んでいるお子さんもいました。
また、ぼんちょは年に1回居住地交流へ行っていますが、希望をすれば回数を増やせることも支援学校の担任の先生から説明がありました。
支援学校の先生と保護者同伴
ぼんちょの学校では、居住地交流に行く時に保護者と支援学校の先生が同伴でした。
なので、とても安心して小学校に行くことができました。
これは、学校によって対応が違うかもしれません。
居住地交流の体験談
- 事前に内容を教えてもらい不安な点は共有
- きょうだいがいる場合はきょうだいにも確認
- 自己紹介は特別支援学校で用意してくれていた
- 難しかったことと楽しめたこと
実際に居住地交流に行った体験について紹介していきます。
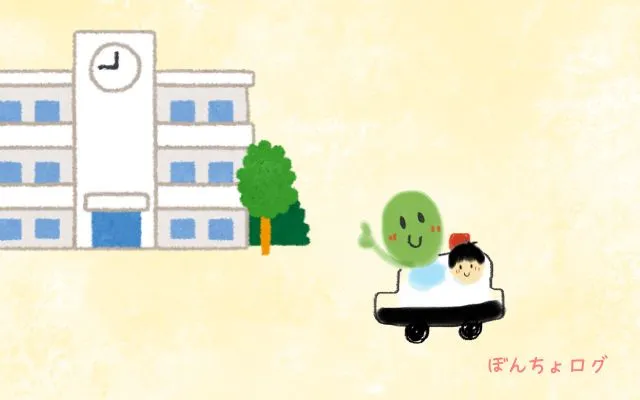
事前に内容を教えてもらい不安な点は共有
- 自己紹介
- リトミック
- サーキット活動
- 紙コップタワー
この内容を体育館で1時間目にすると連絡がありました。
この内容を見たときに心配になったのは「紙コップタワー」。
ぼんちょは、コップは執着するくらい好きでした。
「もしかすると独り占めするかも・・・」
「人が作ったタワーを崩すかも・・・」
という心配がありました。
このことを、支援学校の担任の先生経由で交流先の小学校に伝えてもらいました。
すると、居住地交流当日に小学校の特別支援学級の先生から、
「ぼんちょさんは紙コップが大好きと聞きました。独り占めするのが難しいくらいたくさん用意しているので安心してくださいね。」
と、温かく声をかけていただけ安心できました。伝えておいて良かったです。
きょうだいがいる場合はきょうだいにも確認
学区の小学校へ行くということは、きょうだいがいる人はきょうだい児もそこの学校に通っている可能性があります。
ぼんちょ兄は、もちろん居住地交流先の小学校に通っています。
一応、念のために伝えました。

ぼんちょが今度小学校に1時間だけ勉強しに行くからね。行くのは◯◯学級(知的支援学級の名称)だから、ぼんちょ兄には会わないと思うんだけど・・・
すると、ぼんちょ兄は意外にも嬉しそう。
話を聞いてみると、
周りの子は一緒の小学校に兄弟が通っているのに、ぼんちょは違う小学校に通っている・・・
それをを仕方ないとわかりつつも、少し寂しい気持ちがあったようです。
居住地交流の前日に自宅に遊びに来ていた友達に、
「明日俺の弟が1時間だけ小学校に来るんだ」
と伝えていました。
居住地交流をきっかけに、ぼんちょ兄の複雑な気持ちの1つを親として知ることができました。
自己紹介は特別支援学校で用意してくれていた
居住地交流の当日は自己紹介から始まりました。
特別支援学校から来ている子どもは私たち以外にも複数いました。
みんな支援学校で事前に自己紹介のカードを作成していました。
その内容は当日自己紹介をする段階で初めて知ったのですが・・・
ぼんちょの好きなことの部分に「プラレール」と「草むしり」のカードが貼っていました。
草むしり・・・
私は爆笑でしたが、小学生たちからは「偉い!」なんてコメントもいただいて、楽しい自己紹介になりました。
難しかったことと楽しめたこと
活動内容は支援学校の子も楽しめるように設定されていました。
ぼんちょにとって難しかったことは「活動の切り替え」でした。
活動が楽しいからこそ
まだやりたい!(号泣)
と、リトミック・サーキット活動・紙コップタワー全部が終わるたびに怒り泣きしていました。
活動が終わると、先生のところに集合することで切り替えるきっかけも作ってはくださっていたのですが、受け入れが難しかったです。
でも、小学校の女の子が1人、ティッシュを差し出しながら「大丈夫?」とぼんちょに聞いてくれた瞬間だけは涙が引っ込みました。
小学生のやさしさが感じられて、このことだけでも「来て良かったな〜」と私は思ったりしました。
一番うまく楽しめたのはサーキット活動でした。
コースは1種類ではなく選べるゾーンもあり、ぼんちょは自分のできることを選びながら挑戦できていました。
紙コップタワーは「重ねる」方法で積んでいくことができました。
なんと、人のタワーを1回も壊さなかった・・・!
本当にたくさんの紙コップが用意されていることで満足できたみたいで、人の紙コップにまで手を出さずにすみました。
こんな感じで居住地交流は難しいこともあったけれど、概ね良い経験となりました。
居住地交流以外の小学生との交流
- 支援学校がある地域の小学校との交流
- 障害福祉サービス事業所での交流
居住地交流以外にも小学生との交流はあります。
支援学校がある地域の小学校との交流
全学年ではありませんが、支援学校がある地域の小学校との交流があります。
ぼんちょの学校では3、4年生が歩いて小学校まで行き一緒に活動する機会があります。
障害福祉サービス事業所での交流
放課後等デイサービスや日中一時支援を利用している場合は、そこで小学生と活動することがあります。
ぼんちょは放課後等デイサービスは特別支援学校の子だけが利用する事業所を利用していますが日中一時支援には小学生がたくさんいます。
居住地交流で小学校に行ったときも、日中一時支援で一緒に過ごしている小学生が「ぼんちょ君!」と声をかけてくれ、普段から交流していることを実感しました。
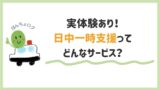
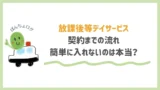
まとめ
特別支援学校に入学後、住んでいる地域の小学生と交流する機会があります。
ぼんちょも特別支援学校に入学後、実際に住んでいる学区の小学校に訪問する機会(=居住地交流)がありました。
居住地交流への参加は強制ではなく希望です。
もしも住まいがある学区の小学生と関わりを持ちたい場合は参加を希望することをおすすめします。
もしも参加するにあたって不安なことがある場合は担任の先生や、担任経由で活動先の小学校に事前に伝えることができます。子どもにとって良い経験となるよう、心配なことは先に伝えておきましょう。
もしも就学前に小学校にするか支援学校にするかを決めるにあたり、支援学校と小学校の交流について気になっている人はこの記事を参考に就学相談などで確認しておくことをおすすめします。
特別支援学校入学後の地域小学校の小学生との交流が気になっているご家庭にとって参考になることがあれば幸いです。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!