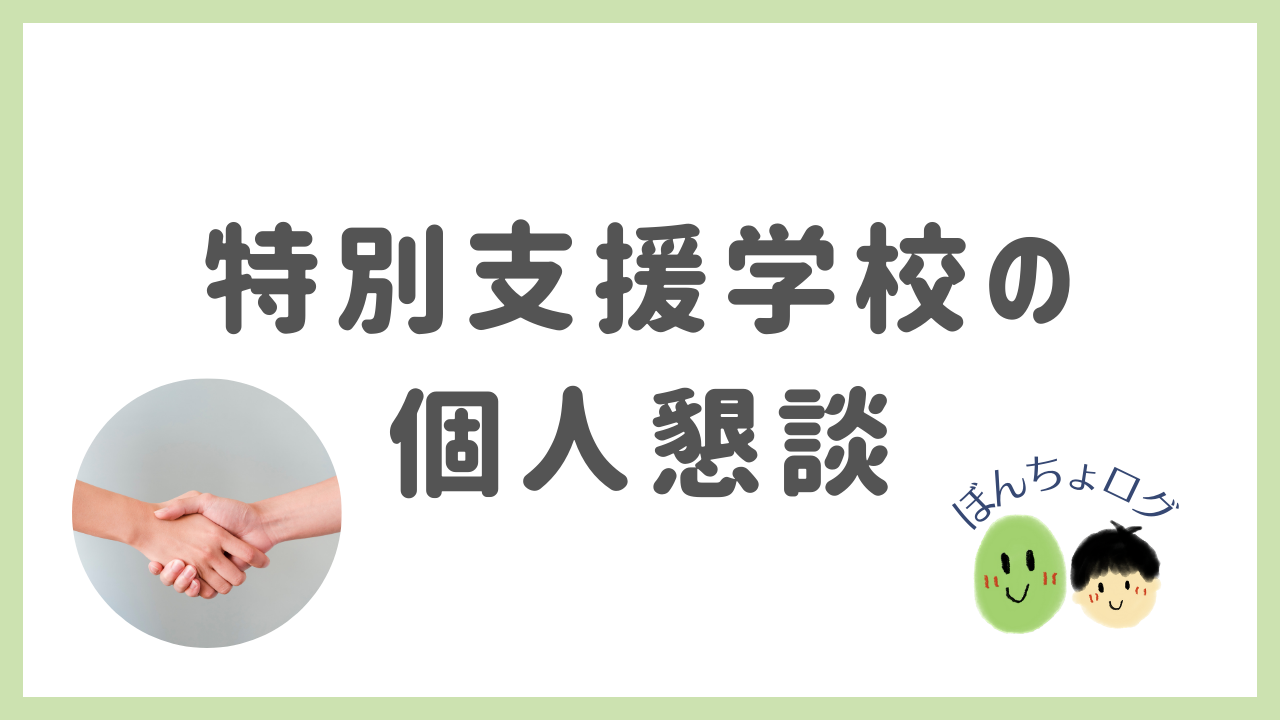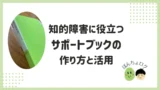特別支援学校の個人懇談で何を話す?
特別支援学校の個人懇談は親にとっては貴重な情報源です。
我が家の重度知的障害児・ぼんちょの実体験をもとに、特別支援学校の個人懇談の実際の様子を紹介してみます。
この記事を読むことで、支援学校の個人懇談のイメージが伝われば幸いです。
特別支援学校の個人懇談の小学校との違いは?
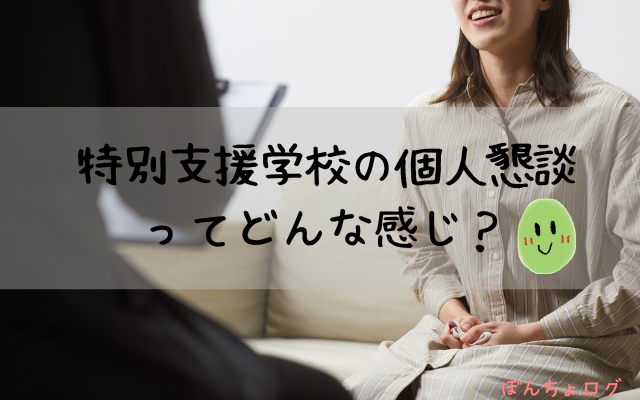
我が家には特別支援学校に通うぼんちょと、地域の小学校に通うぼんちょ兄がいます。
小学校の個人懇談はあっさり。
ぼんちょが支援学校に入学して、とても手厚い個人懇談だったので驚きでした。
学校によって違うかも知れませんが、次のような違いがあります。
| 特別支援学校 | 小学校 | |
| 時間 | 30分枠 | 10分枠 |
| 先生の人数 | 2〜3人 | 担任1人 |
| 評価 | 個別の指導計画 | 通知表 |
1クラス40人に担任1人の小学校
1クラス6〜8人に担任2〜3人の特別支援学校
違いがあって当然です。
小学校では、学期の終わりに「通知表」をもらいますが支援学校にはありません。
支援学校では、代わりに「個別の指導計画」というものがあるのですが、その計画を軸にして学校での様子を教えてもらうことが個人懇談のメインです。
特別支援学校の個別の指導計画って何?
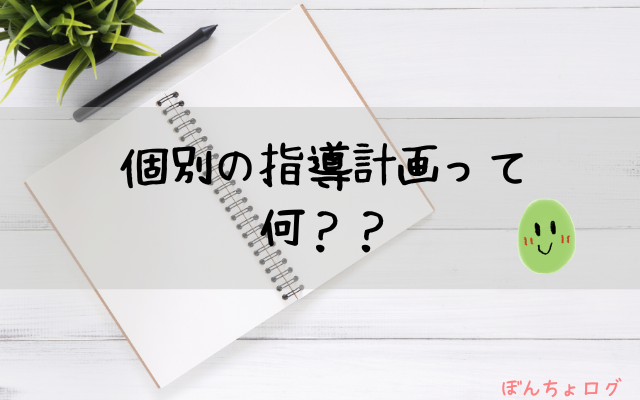
個別の指導計画って何?
支援学校には通知表の代わりに「個別の指導計画」があります。
| 通知表 | ◎◯△の評価:教科ごとの得意不得意がぱっと見でわかりやすい。でもその評定がついた理由がわからない。 |
| 個別の指導計画 | すべて文章で評価が書かれている:どんな支援をして何ができたかが書いてある |
ぼんちょが通う特別支援学校は前期・後期制のため、9月末の懇談で前期の個別の指導計画の評価を渡されます。
「個別の指導計画」には領域・教科ごとに「目標・学習内容」が書いてあります。
そしてそれに対して「どんな支援をして何ができたか」が記載されているのです。
「何をどのように取り組んだか」
「どんな支援があるとできたのか」
親にとってはこれらの情報がとても参考になる資料となります。
個別の指導計画を家庭で活かすには?
特別支援学校で学ぶことはすべて子ども本人の「自立」につながることです。
だから、個別の指導計画で取り組んだことは評価されて終わりではありません。
我が家では受け取った個別の指導計画を見ながら、
学校からの評価
家庭での様子
を比較しておくことを大切にしています。私は次のように整理しています。
| 内容・目標 | 学校からの評価 | 家庭での様子 | 取り組めそうなこと |
| 生活:石けんで手洗い | ・石けんが手につくと手を合わせて洗おうとしたり自分から手を差し出すことがある | ・石けんを手につけた後、親が後ろから手を合わさせている | ・石けんをつけた後少し待ってみる |
| 生単:買い物練習 | ・首から下げた財布からお金を取り出す ・レジの順番待ちが難しく人が減るまで他の場所を歩く | ・親がお金を手渡し、手添えでトレーに置いている ・レジの順番待ちが難しく人が減るまで他の場所を歩く | ・首から下げられる財布に500円玉だけ入れて買い物してみる |
| 国語:絵本の良い聞かせを楽しむ | ・大型絵本だと笑顔で期待する姿が見られる | ・大型絵本がなく普通の絵本しかない。普通の絵本に興味なし | ・学校で普通サイズの絵本にも取り組んでみてもらう |
| 図画工作:花紙で遊ぼう | ・選んだ色の花紙をちぎってペットボトルに入れることができた | ・チラシを破るのが好きだけど、破って終わりになっている | ・花紙を用意して同じことに取り組んでみる |
| 自立活動:2種類のカードから選んで渡して遊びたいおもちゃを要求する | ・遊ぼうとするタイミングでカードの場所を知らせて要求を伝える練習を重ねると自分のタイミングで手に取り渡すことができるようになった | ・カードは作っているが、本人が自由に取れる場所にカードの設置ができていない | ・学校で使用しているのと全く同じ形式でカードを用意してみる |
学校と家庭の様子を比較することは、子どもの状態を理解する助けになります。
そして「家庭でも取り組めそうなこと」を炙り出せるのです。
学校と家庭という異なる環境における我が子を把握することが我が子をより理解することにつながります。

懇談で聞いた内容や、個別の支援計画に書いてあることで、よくわからないことやもっと詳しく知りたいことがあったら先生に尋ねています。例えば、絵カードについては実物を見せてもらい写真に撮らせてもらうなどします。
特別支援学校の個人懇談で家庭から伝えること
私はそもそも連絡帳を日記代わりに利用している人なので、普段からぼんちょの家庭での様子を逐一伝えている保護者です。
それでも個人懇談の時には必ず
「ご家庭から何かありますか?」
「最近のご家庭での様子はどうですか?」
と尋ねられるのです。
なので、私は個人懇談前に2つの準備をしています。
家庭で見られる問題行動について
私は個人懇談で「家庭で見られる問題行動が学校でも見られるかどうか」は毎回尋ねます。
ぼんちょの場合だと、「投げる」行動はずっと現れやすいものなので、注意しておいてもらうためにもほぼ毎回の個人懇談で話題に出すようにしています。
家庭での様子がわかる写真や動画の準備
個人懇談で我が子の様子を伝える時、「実際に使っている物」や「家庭での行動」は、写真や動画を見せる方が言葉よりも伝わりやすいです。
なので、私は毎回パソコンに「懇談フォルダ」を作成して、様子のわかる写真や動画をぶち込んでいます。

「わかりやすい」と先生からも好評なので続けています。
過去の特別支援学校の個人懇談でありがたかったエピソード

個人懇談の時に先生からしてもらえてありがたかったな〜ということをブログにまとめてみます。
動画や写真で保護者に説明してくれた
ぼんちょが通う支援学校では、懇談時に毎回ぼんちょの学校での様子を撮影した動画や写真をiPadで見せてもらえます。
・話で聞くよりも、様子がわかりやすい
・動画・写真という記録に残っているので間違いない情報
このような理由からとても良い取り組みだし良い時代だなと感じます。
実際に使用しているものを見せてもらえた
特別支援学校の教室に入ることが参加日と個人懇談くらいしかありません。
なので、懇談の時は、ぼんちょが学校で使用しているアイテムを実際に見ることができるチャンスです。
支援学校で使用している「支援アイテム」「課題」「おもちゃ」についてはお願いして実物を見せてもらいます。

見せてもらえたら記憶より記録。写真に撮って持ち帰るようにしています。
特別支援学校の個人懇談が終わった後にすること
関わりがある支援者と情報共有
個人懇談が終わった後、学校での様子と家庭での様子を比較して取り組めそうなことを探すことは最初に話しました。
それとともに大切なのは、学校以外に利用している福祉サービスに懇談で得た情報を伝えることです。
特に放課後等デイサービスを利用している場合、療育内容の参考にする場合があるため必ず伝えます。私は次のものを手渡ししています。
懇談で話したことを自分なりにまとめたメモは、最近では作成をchatGPTにお願いしています。
録音はしていないので、懇談で話した内容をすぐに箇条書きで打ち込み、
「療育の先生の報告します。A4用紙1枚のWord形式に収まるよう作成してください。」
と伝えると、およそ良い感じに仕上げてくれます。便利な世の中です。
サポートブックに記録
もしサポートブックや成長の記録を作成している場合は、懇談で得た情報は記録しておくことをおすすめします。
サポートブックは懇談前や懇談後に更新すると決めておくと常に最新の情報を保てます。
まとめ
特別支援学校の個人懇談で何を話す?という質問に重度知的障害児ぼんちょの実体験をもとにブログでまとめました。
学校ごとで違う面もあるとは思いますが、写真や動画を活用して情報共有していくことはとてもおすすめできる方法です。
支援学校は個々に合わせた支援アイテムも豊富です。個人懇談など学校に足を運んだ機会を利用してしっかり見せてもらいましょう。
支援学校でのお子さんの様子には家庭で活かせる情報がたくさん含まれています。
個人懇談をお子さんを理解する1つの機会として活用していきたいですね。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!