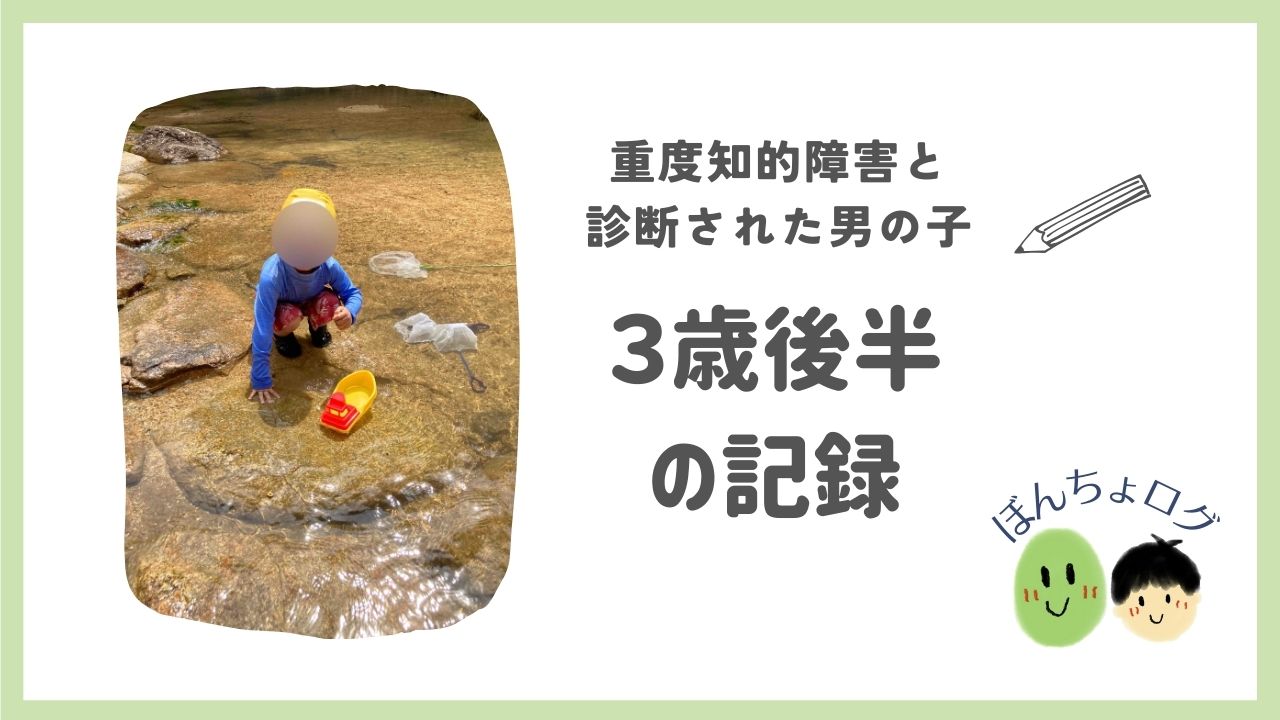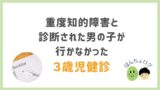我が家の重度知的障害と診断された「ぼんちょ」の3歳後半の成長や特徴的だった行動をブログで紹介します!
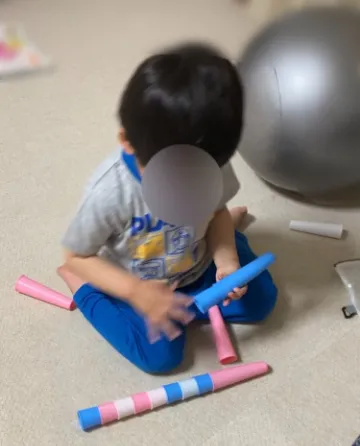
重度知的障害児「ぼんちょ」の3歳児後半時期(4歳前)の特徴や成長の記録をブログにまとめます。
ここに書いてある4歳前の成長記録がすべての知的障害の子どもに当てはまるわけではありません。
ひとりの重度知的障害の男の子の過去の記録として誰かの参考になれば幸いです。
3歳後半の特徴の前に!3歳半までのおさらい〜療育手帳取得

なかなか身辺自立など生活スキルが身につかないぼんちょと、毎日コツコツ取り組む日々でした。
重度知的障害と診断された子の3歳7ヶ月から4歳までに「できるようになったこと」と「困りごと」
ぼんちょの3歳後半の発達の成長記録をブログにまとめます。
この時期は児童発達支援センター利用から1年が経つ頃です。
3歳後半にできるようになっていたこと

- 外出後の手洗いの習慣化
- 手を叩いて「ちょうだい」と要求できるようになる
- ズボンに足を入れようとする
- ファスナーの開け閉めができる
- 室内ジャングルジムに登る
- 色の違いを理解して、ブロックで遊ぶ時にに同じ色を重ねないようにするなど規則的な遊び方が見られる
- 「できた」「褒められた」がわかり、相手と一緒に笑ったり、自分でも喜ぶことが増える(両手を挙げてパタパタ)
家庭と療育先の児童発達支援センターとで連携し、目標を共有して毎日コツコツと積み重ねてきた1年間。
少しずつ「できるようになった」「理解が進んだ」と小さな成長を感じられることも出てきました。
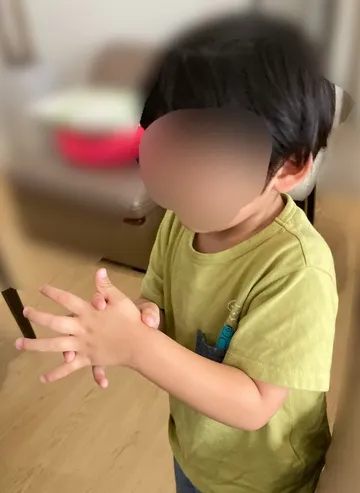
3歳後半ごろに感じた困りごと
3歳後半に次の困りごとにぶち当たりました。
進級をきっかけにできていたことができなくなる
ちょうど1年が経つということは「進級」の時期です。
「進級」という環境の変化で初めて経験することになるのです。
できていたことが
振り出しにもどる
そんな経験を。
- 靴を箱に片付ける習慣がなくなった
- トイレでの排尿成功がゼロに
1年間取り組んできて少しずつ進歩していたことが「ゼロになる」という経験をしました。

新年度の何となくバタバタしている時期に集中できないことが続いて、できていたことが消失していくという感じでした。トイレでの排尿は、ここから4年成功無しです。
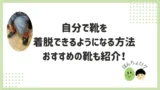
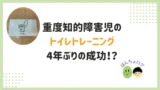
機会が減るとできなくなる
ちょうどコロナ禍で練習を繰り返して少しずつマスクをつけることできるようになってきていました。
ところが、コロナ禍が落ち着いてきてマスクをつける機会が減ると途端につけるのを嫌がるように。
しっかり定着していない場合は特に、機会が減った途端できなくなるということを実感しました。

身体や知能の成長で困り事が増える
- 高いところに登りたがる
- 理解できるからこそ応じない
こんな困りごとが出てきました。
高いところに登りたがる
体の使い方が上手になってきたことで、室内の高い場所にもよじ登るように。
踏み台を見つけては移動し、欲しいものを取ろうとする場面が増えました。
大人が驚いて注意すると、嬉しそうに反応する(→行動強化の恐れ)ため、家庭では「高いところに物を置かない」など環境調整で対応しました。
「できること」が増えると、それに伴って新たな課題も生まれてくることを実感した時期でした。
理解できるからこそ応じない
実物やカードを見せて移動したり活動を切り替えたりしていましたが、次に何の活動があるか理解した上で応じないことが増えました。
理解できるようになったこと
意思表示できるようになったこと
これらは成長です。
ですが、生活の中で次の活動がやりたくないことだったら拒否してすぐには応じないということも増え、スムーズにいかないことが増えてきました。
重度知的障害3歳後半の特徴的だった行動の記録
重度知的障害児ぼんちょが3歳後半だった頃に見られた特徴的な行動を記録します。
大人に型はめやパズルを何度も繰り返しはめさせる
3歳後半の時期は大人と一緒に遊ぶことがデフォルトのぼんちょ。この頃、木製の型はめパズルやトーマスやアンパンマンの紙パズルが好きでした。
「好きでした」と言っても、自分ではめる能力がありません。
ぼんちょは、人にはめてもらって自分で崩すのが好きでした。

完成後すぐに崩されるという虚無感を味わうこと何億回・・・(数えてないけど)
はめるところをひたすらじーっと見ていて、完成すると崩すの繰り返し。
この頃ひたすらぼんちょに付き合ってはめてあげていました。
匂って確認する
3歳後半ごろから食べ物を匂って確認する姿がよく見られました。
「食べられるかどうか匂いで確認してるのかな?」と思うじゃないですか。
ですが、人に対しても匂うことがたびたび見られました。
児童発達支援センターの先生だとか、公園にいたおじさんとか(全力で止めたし謝った)。
匂いがぼんちょにとっての理解の手段の1つになっているのか
匂うことが好きなのか
よく匂いを嗅いでいます。小学生になった今でも。
重度知的障害3歳後半の出来事の記録
利用していた日中一時支援が引越し
ぼんちょが利用していた日中一時支援が場所を移転しました。
これまでに、保育園から児童発達支援センターに生活の場が変わることや引越しも経験しているぼんちょ。

場所が移動するだけなんだから、さすがに何の問題もないでしょ。楽勝!
と思っていた私。ですが、なんと大号泣!!!
それまでは人見知りも場所見知りもしなくて、なんて楽なんだ!
と思っていたため、とてもびっくりする出来事でした。
ぼんちょの理解力が成長し、
初めての場所=不安
と感じるようになったのかもしれません。

小さい頃平気でも、成長して情緒が育つことによって不安になることもあるんだな〜思った出来事でした。
3回目のMRI検査

重度知的障害児ぼんちょ、コロナ禍に3度目の造影剤を使用してのMRI検査を受けました。

検査までの間、大人しく過ごせるよう「お気に入りのおもちゃたち」を持って行かなければ・・
そんなことを思って準備をするととんでもない荷物量になった思い出。
結果は、前回から病変の大きさ等に変化なし。
経過観察は必要で、次は2年後に再検査という結果でした。
まとめ
重度知的障害児「ぼんちょ」の3歳児後半時期(4歳前)の特徴や成長の記録をブログにまとめました。
3歳後半のぼんちょは、これまでの積み重ねが少しずつ実を結び、「できること」や「伝えられること」が増えました。
一方で、環境の変化や機会の減少によってできていたことがリセットされる難しさや、成長ゆえの新たな課題にも直面しました。
この時期は、「成長=すべてが楽になる」ではなく、できるようになったからこそ起こる困りごとにも向き合う必要があることを実感した日々でした。
同じ「重度知的障害」と診断されても、子どもの成長のペースや特徴は本当にひとそれぞれ。
このブログが、同じような立場の方にとって「わかる」「参考になる」と感じていただけたら嬉しいです。
これからも、ぼんちょの成長を記録しながら、小さな「できた」を一緒に喜んでいきたいと思います。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!