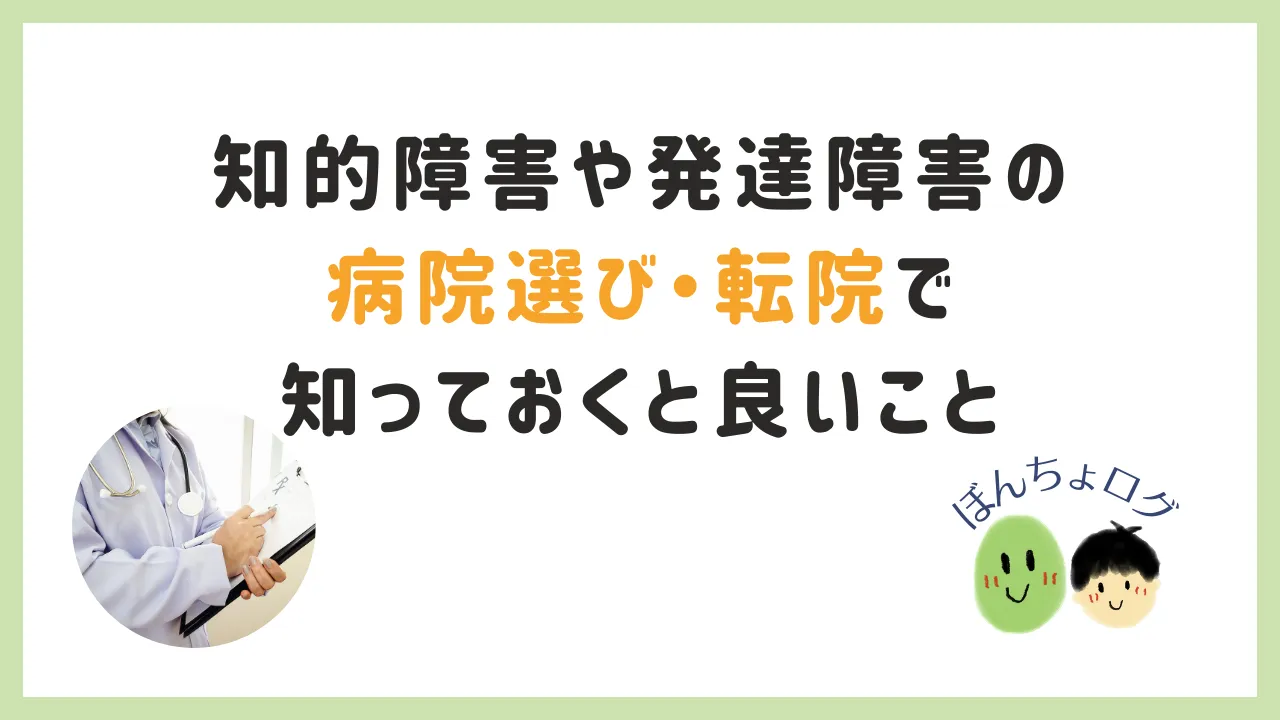知的障害や発達障害の子どもの病院選びについて、4つの病院のお世話になった重度知的障害児「ぼんちょ」の母親パトまめが解説します。
知的障害や発達障害のある子どもの病院選びや転院についてブログに経験をまとめます。
「どの病院・診療科がいいのか分からない」
「今通っている病院で本当にいいの?」
といった迷いや不安がつきものです。
健診や保育園・幼稚園で指摘を受けて初めて受診先を探す場合もあれば、現在の病院に納得できず、より適した医療機関を探している方もいるでしょう。
この記事では、実際に重度知的障害と診断されたぼんちょの病院選びや転院をどのようにしてきたか紹介します。
知的障害や発達障害を理由に初めて医療機関にかかる・病院を選ぶ時に知っておくと良いこと
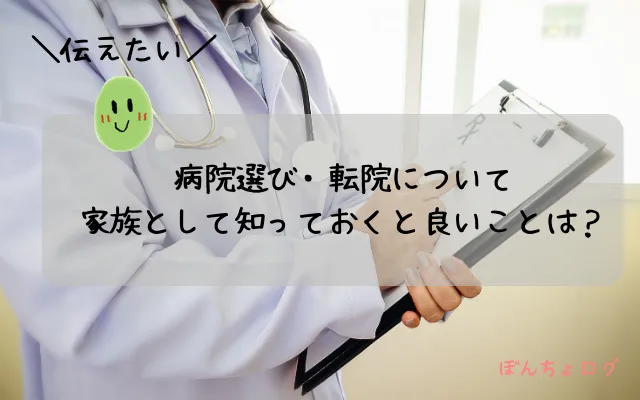
実際に最初はどうやって病院を選んだの?
初めて病院を選ぶ・・・と言っても、実際には自分で一から選ぶ人はとても少ない気がします。
ぼんちょの時も、最初は自分で選んだというよりは、かかりつけの小児科の先生が2つの病院を提案してくれ、そのうち大きい病院を選んだだけでした。
ですが、その後のぼんちょの状態や家族の希望に合わせて、複数の病院に転院しています。このように、最初に選んだ病院にずっとお世話になる必要はないということを、多くの人に知ってもらえれば幸いです。
病院選びで最も大切なのは何か?
結論から言うと、病院選びで最も大切なのは、
家族にとって
「スピーディーに」
「必要な支援につながるための」
サポートをしてくれるかどうかです。
地域にもよりますが、知的障害や発達障害を理由に新規で病院に通うとなると、予約は数ヶ月単位で埋まっていることが多いです。「この病院が良い!」という希望がないのであれば、通える範囲の病院で半年以内に受診できるところを探すのをおすすめします。

病院にまずかからないと療育などの実際の支援を受けるのも遅くなってしまいます。
病院に行くのには人それぞれの理由があります。
障害について検査したい
診断書や意見書などの書類が必要
言語療法や作業療法を受けたい
薬を処方してほしい
どの病院でもできるのでは?と思いきや、経験上そうと言い切れません。
たとえば、言語療法や作業療法は実施していない病院もたくさんあります。
もちろん病院にかかった後で新たに必要な支援が見えてくる場合もあります。かかっている病院では必要な支援が受けられない状況になった時は、他院に紹介してもらうことも考えましょう。
それぞれの病院で「何ができるか」「その病院や医師の方針」は、その病院にかかってみないとわからないことがほとんどです。
子どもを育てる過程で、家族や本人にとって必要な支援も変わります。
今かかっている病院では実現が難しいことが出てきた時点で転院することは可能です。
ただし、どこの病院も新規予約の待機時間は長い可能性があるため、転院を決意する場合は早めに行動することをおすすめします。
そもそも病院では何をしてくれるの?
重度知的障害ぼんちょが、病院(医療機関)で過去にしてもらったことは次のとおりです。
- 知的障害につながる原因を調べる検査(MRI検査・染色体検査・代謝異常検査)
- 発達検査(遠城寺乳幼児分析的発達検査・新版K式発達検査)
- 診断
- 作業療法
- 補助を申請するための意見書・診断書(日常用具給付や特別児童扶養手当など)作成
- 療育を受けるための診断書作成

ぼんちょはしてもらっていませんが、薬の処方や就学前に特別支援教育を受けるための意見書作成、子どものや家族のカウンセリングを病院でしてもらった人も周りにいます。
つまり、病院ができることをまとめると次のとおりです。
病院がしてくれること
病院ではしてくれないかもしれないこと
健診や保育園・幼稚園で子どもに発達について指摘を受けた時、まず病院に行くことになる人は多いです。この時の親の心理状況を想像してみてください。
子どもに障害があるかも。
できれば嘘だと言ってくれ。
ですが、そんな風にショックを受けている保護者の複雑な気持ちとは反対に、障害がある前提で話が進んでいくことが多いです。指摘されたり何らかの困り事があって来院している以上、「障害がある」「障害の可能性がある」と証明して必要な支援につなげることが医師の仕事です。
なので病院に行く以上、医師は「障害がある」「障害の可能性がある」と思って対応してくれることがほとんどです。なので、「病院で我が子の障害の疑いを消してくれるかも」と期待して受診することはおすすめできません。

障害の疑いを誰かに否定してほしい気持ちが保護者としてよくわかります。そのためにドクターショッピングしたくなる気持ちもとてもわかります。ですが、「障害がある」「障害がない」という医師の言葉で目の前の我が子は何も変わりません。診断は必要な支援のためにあるだけです。
療育を受けるのに必要な診断書の作成はしてくれますが、実際に通う療育先については自分で探すよう言われることが多いです。住んでいる地域から通える療育の事業所については次の方法で情報収集できます。
- お住まいの自治体に問い合わせる
- 相談支援事業所で相談する
例外として、かかっている病院が運営している児童発達支援事業所がある場合や、主治医が指導・監修している事業所がある場合には病院で勧めてもらえることもあります。
病院がしてくれないかもしれないこと
病院や医師によって方針が異なりやすいこと
これまで実際に病院にかかったり他の保護者の話を聞いて、病院や医師の方針によって対応が異なりやすかったことを経験を踏まえてお伝えします。
作業療法や言語療法を実施している病院ならば希望すれば必ず受けられるかというと、病院によって違いました。
希望すれば受けられる病院
子どもの発達段階を見て決定される病院
毎日療育に通っていない間だけ受けられる病院
ぼんちょが住む地域でもこのように病院によって違いがありました。
作業療法や言語療法を受けたいのに病院(医師)の方針で受けられない場合、家族として後悔が残るかもしれません。その場合は、通える範囲に希望すれば受けられる病院があるのであれば、転院を希望してみても良いのかもと個人的に考えます。

作業療法・言語療法は月1・2回のことが多く、重度知的障害児のぼんちょ自身が月2回の作業療法によって劇的に変わるということは正直ありませんでした。でも、親としては勉強になりました。
投薬も不思議なくらい、あの病院(医師)は「薬を出してもらえやすい」「薬をなかなか出してくれない」と保護者の間でうわさ話になることの1つです。
投薬する・しないは、安易に決められることではありません。そして正解がないことです。
投薬は障害を治すものではなく、合併して現れる不眠や衝動性などに対して一時的に効果を発揮するものです。そして副作用が現れる場合があります。
なので、多くの場合は薬以外の環境調整などできることをしてから投薬を考えることになります。
ですが、生活の中で本人や周囲に命の危険が生ずる場合などはどうしても必要なことがあります。必要を感じるのに医師の方針で処方してもらえない時などは、転院を検討する必要があるかもしれません。

病院ごとのこういった違いはGoogle検索ではなかなかたどりつけません。親の会や同じ療育に通う保護者同士の話からわかることが多いです。最近はLINEのオープンチャットなどで地域の情報を匿名で交換できるコミュニティも増えているので、お住まいの地域でそういったコミュニティを探すのも情報収集の方法の1つです。
リハビリや投薬などについて、家族としてお願いしたいのに希望が通らない時は他院に転院してみるのも方法の1つかもしれない(もちろん医師にも考えがあってのことだということは頭に置く必要あり)
知的障害や発達障害の子が通う診療科の種類
知的障害や発達障害の子が通う診療科としては次の診療科が挙げられます。
| 小児科 | ・子どもの心と体の発達のサポートをしてくれる ・発達障害や知的障害の診断をしない小児科もある |
| 小児神経科 | ・子どもの脳・神経などに関する病気やてんかん、知的発達の遅れ、発達障害などをサポートしてくれる |
| 児童精神科 | ・発達障害や子どものこころの問題、不登校などをサポートしてくれる |
重なっている部分はありますが、子どもの発達・障害のことで病院にかかる場合に次のように考えるとわかりやすいかもしれません。
身体の発達で気になることが多い・・・小児科・小児神経科
脳や神経を調べてもらった方が良いかも・・・小児神経科
子どものこころや行動、精神面の発達に心配な点がある・・・児童精神科
知的障害や発達障害の診断は小児科・小児神経科・児童精神科いずれでも可能です。
ただし小児科は、発達外来のある小児科でない場合は他院に紹介されることが多いです。
ちなみにぼんちょの場合は、発達の遅れを指摘されたときに「身体の発達が遅い」「それ以外の発達も遅い」状態でした。そのため、脳や神経に病気が隠れていないか一度診てもらう方が良いとの理由から初めてかかった診療科は大学病院の「小児神経科」でした。
医療機関を卒業するときは来るのか?
障害の診断がなく、幼少期に療育を受けるために医療機関を受診していたけれど日常生活で不都合が減り、問題なく生活を送れているような人は医療機関をいったん卒業する人もいるでしょう。
障害の診断を受けた場合は医療機関とお付き合いし続けることになります。障害を理由に様々な支援を受ける時にはその根拠として医療機関の診断書や意見書が必要になることが多いです。
特に、障害年金を受給する可能性がある場合は診察歴が支給の判断に利用されることがあります。療育手帳を取得している人は発達検査を児童相談所で受けることも多く、医療機関に用がない人もいるかも知れませんが、定期的にかかる医療機関を持つことをおすすめします。
病院選び・転院の実際は?

実際にぼんちょがどのように医療機関(病院)にかかり、他の病院へ転院してきたか経験をブログにまとめます。
かかりつけ小児科から専門病院(大学病院小児神経科)への紹介
1歳半健診や3歳児健診は、医療機関を受診するきっかけになりやすい出来事です。ぼんちょも、1歳半健診を控えた時にかかりつけの小児科医と相談して専門医療機関への受診を決めました。
かかりつけの小児科には発達外来はなく、小さい診療所で検査等もできないため大学病院の小児神経科への紹介状を用意してくれました。
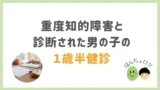
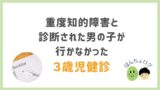
大学病院の小児神経科から作業療法がある病院の小児神経科への紹介
大学病院の小児神経科では次のことをしてもらいました。
- 発達検査(遠城寺乳幼児分析的発達検査)
- 知的障害につながる原因を調べる検査(MRI検査・染色体検査・代謝異常検査)
- 療育を受けるために必要な診断書作成
上記以外に、作業療法を受けることもできることを教えてもらいました。ただし、その大学病院には作業療法がないため、受ける場合には他院に紹介となるとのことでした。
受けてみたいとお願いすると、他院への紹介状を作成してくれました。

ぼんちょはMRIで白い病変があるため以降その病変の定期的チェックが必要となりました。なので、完全転院ではなく新たに通う病院が増えるという形でした。MRIの定期チェックは大学病院で、作業療法は別の病院で受けることになりました。
作業療法を受ける病院を転院
ぼんちょは大学病院から紹介されたA病院で作業療法を受けていました。A病院では3ヶ月に1度の小児神経科医師の診察と1ヶ月に2回の作業療法でお世話になりました。ですが、次の理由から転院を決意しました。
- A病院は他市で通院に時間がかかる
- 住んでいる市内でリハビリに強いB病院があるとの情報を得た
A病院でお世話になった作業療法士も良い先生で悩みましたが、「あの時転院していたらどうなったのだろう?」とあとで後悔したくないとの理由からB病院への転院を決断しました。
B病院に転院する時にA病院の先生から、「B病院の診療科は小児科と児童精神科とあるけれど、どちらにする?」と相談されました。
小児科と児童精神科とのちがいを教えてもらった上で、当時はこころの問題よりも知的な遅れと身体の発達への心配が大きかったため小児科へ紹介してもらうことを決めました。
B病院では次のことでお世話になりました。
- 作業療法
- 補助を申請するためなどに必要な意見書・診断書(日常用具給付や特別児童扶養手当など)作成
A病院の頃と変わらず、B病院でも3ヶ月に1度小児科医の診察があり、1ヶ月に2回作業療法を受けました。
ところが、次の転機が訪れます。
当時、ぼんちょは保育園に通いながら週1の療育に通っていました。ですが、保育園退園に伴い引越しをし、引越し先の児童発達支援センターで毎日療育に通うことが決まりました。
B病院は、引越し先からも通える範囲ではありましたが、B病院の作業療法士から「B病院では、毎日療育に通い始めたら作業療法をいったん終了する方針になっている」と告げられました。
毎日療育に通い始めて慣れた頃、予定どおり作業療法は終了となりました。そこから先は、何か申請をするために診断書が必要などの理由がある時だけでにB病院を予約して受診する形になりました。
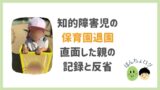

作業療法の終了と引越しを機に住まいの近くの小さい診療所に転院
B病院には作業療法を目的に通っていました。B病院の小児科の先生はとても良い先生でしたが、通うのに片道1時間かかる距離が負担です。
たまたま引越し先の近くの小児科に、小児神経科外来がありました。そこで相談するとB病院からの紹介状があれば受け入れ可能とのことでした。そこでB病院から転院することに決めました。
今現在は、その診療所の小児神経科外来に通っています。そこでは次のことをしてもらっています。
- 3ヶ月〜半年に一度30分の診察(日常の困りごとを相談)
- 補助を申請するためなどに必要な意見書・診断書
我が家にとっては4つ目の病院です。ここの診療所は決して大きい病院ではありません。ですが、最初の診察で主治医から次のように言われました。
もしも、ここの病院ではできないことでも、ご家族の方がやってみたいことがあったら何でも相談してください。それがお子さんやご家族にとって必要なことであれば、一緒に考えて実現できるよう助けるのが僕の仕事です。
この言葉を聞いた時に、この医師は私たち家族にとって必要な支援を一緒に考え、支えてくれる医師だと感じました。
年に数回ある診察の時に、
身体で気がかりなこと
家での困りごと
学校での様子
利用している福祉サービスでの状況
色々な話を聞いてもらっています。たくさんの病院にかかったからこそ分かることですが、ここまで丁寧な診察をしてくれる医師は珍しいです。良い主治医に巡り逢えたなと思います。
現在は大学病院での脳の経過観察も継続中で、障害全般については小さい診療所の小児神経外来の主治医に対応してもらうというスタイルで落ち着いています。
転院や紹介状のおすすめの依頼方法は?
転院をしたい
紹介状を書いてほしい
こういった時に「医師を不快にするのでは?」と心配になる人もいます。そんなことは気にしなくて良いのですが、気になる人もいます。
私が今まで周りの人から聞いて良いなと思った方法は、受付に電話して先に伝えておく方法です。転院のための紹介状をもらうには診察が必要ではありますが、先に電話をして伝えておくと当日の話が短くて済むため精神的な負担が少なく済みます。
今後の転院への展望
小児科・小児神経科・児童精神科はいずれにしても「子ども」が対象です。一般的に15歳までとされていますが、病院の方針や主治医の方針にもよるのでかかっている病院や医師に聞いてみるのが一番です。いずれ転院しなければならないときのために余裕を持って確認しておくことをおすすめします。
我が家の場合は、聞いてみたところ「障害年金を申請する時までかかっていても大丈夫。もちろん中学生くらいから大人対象の病院・診療科に変わる人もいる。そうしたい場合は転院先に紹介状を用意します。」と言ってもらえました。
それを聞いて、障害年金の書類を次の転院先の医師にお願いするならば、その時期より少し早めに転院した方が良いのかもと思いました。
今後も子どもの成長やそのときの状況に合わせて、その都度お世話になる病院を探していくつもりです。
まとめ
知的障害や発達障害のある子どもの病院選びや転院についてブログに経験をまとめました。4つの医療機関にお世話になりましたが、その都度、家族や本人に必要な支援が手に入りそうな病院を選んできました。
子どもと医療機関に行くのは実は結構大変だったりします。
なので納得できないことがある場合や、他の病院に転院してみたい理由ができた時には転院を検討するのも一つの方法です。
もちろん選ぶ病院によって子どもの状況が大きく変わるとは限りません。病院選びは家族の納得感の問題だと、みずからの転院経験を通して感じています。
少しでも大変な子育てをしているご家族が、支えになるような医療機関に出会えると良いなと思います。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!