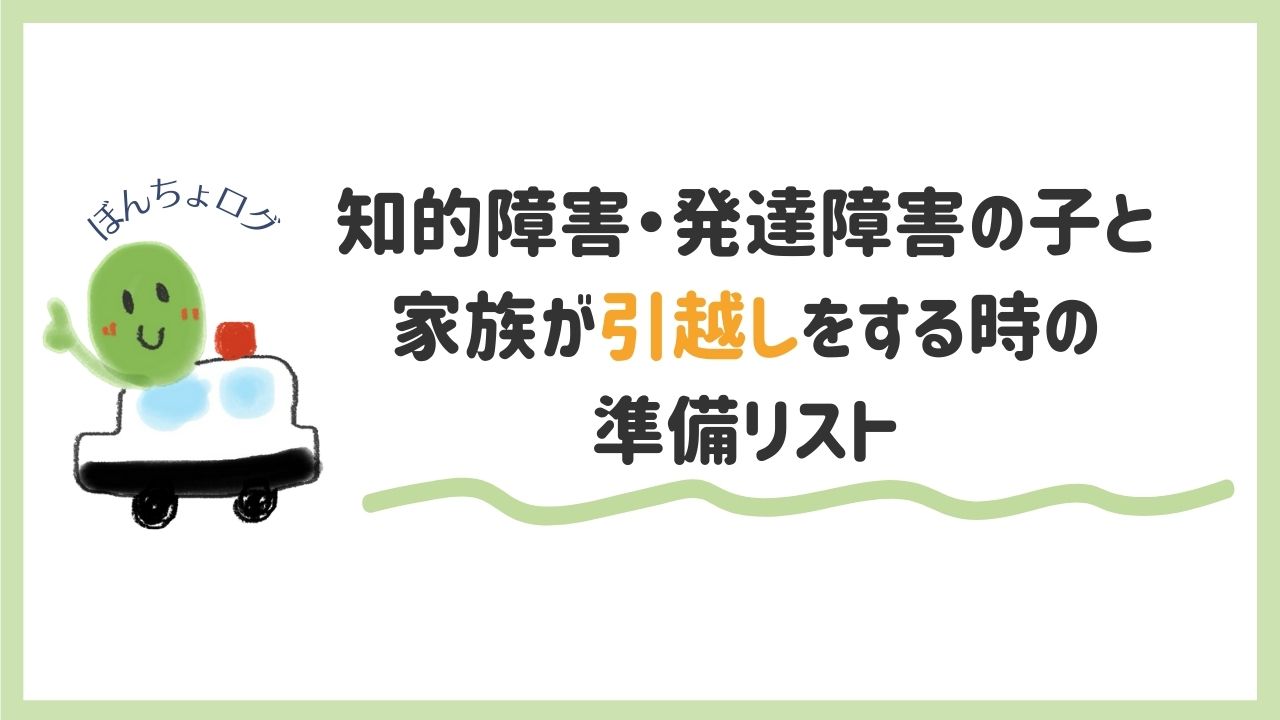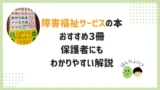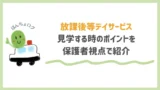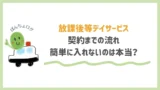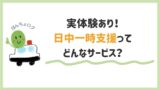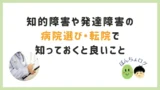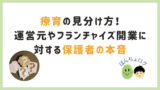重度知的障害児「ぼんちょ」を育てている我が家は、2020年4月に引越しを経験しました!

お母さんは仕事をしながら引越しの準備が大変だったんだよね。
障害児がいる家族の引越し手続きについて、注意すべき点とやるべきことをブログでまとめます。
「知的障害や発達障害の子がいる家庭の引越し手続きについて一番詳しい情報が載っているのはこのブログ!」
そう言ってもらえることを目指して実際の経験もふまえて説明します(自分でハードルを上げる)。
知的障害児の家族が引っ越すときに必要な障害福祉制度の手続きリスト

引っ越し前に、現在利用している障害福祉制度を把握しましょう。
利用している障害福祉制度の把握をしておく
現時点で利用している障害福祉制度について、引っ越し先での手続き方法の確認が必要になります。
まずやることは次のとおりです。
引っ越す場合に手続きが必要な障害福祉制度には次のとおりです。
- 療育手帳
- 通所支援サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス:いわゆる療育)
- 日中一時支援
- 移動支援
- ショートステイ
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 児童福祉年金
- 日常生活用具給付(オムツなどに対する補助)
こういった障害福祉制度を利用している場合、引っ越しに伴い手続きが必要です。
手続き方法の確認は、絶対に引っ越し先(転入先)の自治体の役場にたずねてください。
障害福祉制度は自治体ごとに内容や利用条件、手続き方法がかなり異なります。
なので、必ず引っ越し先の自治体に確認してください。
引っ越しする時の療育手帳は?手続きや知っておきたいこと

療育手帳は大切な証明ですよね。
引っ越しの際の手続き方法や知っておきたいルールを説明します。
順番に説明します。
まず、引っ越しの際の療育手帳の手続き方法は、都道府県をまたぐか否かで次のとおり変わります。
| 都道府県内での引っ越し | ・住所変更のみの手続き |
| 都道府県をまたぐ引っ越し | ・前住所地での判定を引き継いで再発行 ・引越し先の自治体の基準で再判定して再発行 |
都道府県内での引越しにおける療育手帳の手続き
都道府県内での引越しでは、療育手帳を引っ越し先の役所に持って行けば手続きできます。
ぼんちょの引越し先の自治体だと療育手帳を役所に持って行って、書類に必要事項記入(住所変更)だけでOKでした。
都道府県をまたぐ引越しにおける療育手帳の手続き
再発行するために必要らしいです。顔写真!
それから前の自治体で発行してもらった療育手帳も必要です。
判定は、基本的に引っ越し前の自治体の判定が使える場合は引き継がれます。
引き継ぐためには「申立書」を提出することになっています(引っ越し先の役場でもらえます)。
ただし前の自治体の判定を使用できず再判定が必要な場合があります。
これは療育手帳制度が自治体ごとに実施され等級区分(AやBなど)も自治体によって違うからです。

困る・・・
引越しで忙しいのに児童相談所で発達検査を受けろってこと?
もしも検査受けたばかりだと次の検査はすぐ受けられない可能性があるし療育手帳が無い期間ができるのは困る。。。
ただし、2025年7月現在の情報で、療育手帳判定基準の全国統一化を目指す動きがあります。もしも全国統一化されれば、引っ越しをしても引っ越し前と変わらず障害福祉サービスが受けられるようになるのでは?と期待されています。
引っ越しにおける療育手帳の手続きで困らないために、次の療育手帳のルールを把握しておきましょう。
知っておきたい!厚生労働省が自治体に通知している療育手帳のルール

もしも療育手帳の手続きが負担だなと感じた時には、今から紹介する厚労省からの通知を持って行くと引越し先の自治体と交渉できるかもしれません。
「転居に伴う療育手帳の取扱いの留意事項について」という厚生労働省が自治体に通知しているルールがあります。
- 転居してもなるべく再発行ではなく記載事項の変更のみで療育手帳を継続使用できるよう徹底すること
- やむを得ず再発行する場合はできるだけ本人や家族の負担を減らす対応をすること
厚労省は次のことを自治体に通知してくれています。
- なるべく再発行はせず継続使用
- 再発行する場合は本人や家族の負担を減らす
もしも再発行する場合には負担を減らすために次の対応をするよう通知に記載があります。
- 本人や家族から「申出書」で希望した場合は引越し前の地域での判定資料を使う
- 新しい手帳ができるまでの間は前の療育手帳を使用してOKにする
- 前の手帳に書かれてある大切な情報は新しい手帳に引き継ぎ転記する
この通知の中で自治体ごとに等級区分がちがうためにやむを得ず再発行する場合もあることが同時に記載されています。
ですが、極力本人や家族の負担を減らすことを自治体には通知していますので、この通知の内容を引越し先の自治体職員に確認しながら可能な限り少ない負担で手続きできるようお願いしてみましょう。
引っ越し前後に療育手帳の手続きでやることリスト
転居時の療育手帳の手続きについて「引っ越し前」と「引っ越し後」にやることをまとめます。

再判定が必要な場合は児童相談所などで検査を受けることになります。
また、自治体によって基準が違うために引っ越し後の自治体では療育手帳がもらえないことも起こりえます。その場合に、取得できる場合には精神障害保健福祉手帳を取得する人もいます。
引っ越し後の療育はどうなるの?手続きや知っておきたいこと

転居前に療育へ通っていた場合、新天地でなるべく早く療育をスタートしたいですよね。
手続き方法や気をつけるべきことを説明します。」
引越し前後の療育に関する手続き方法や知っておきたいルールを説明します。
- 受け入れ可能な療育の通所支援事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)を探す
- 引越し先の「通所受給者証」の手続きルールを調べる
- 療育を利用できる運用ルールは自治体ごとに異なる
- 療育内容の引き継ぎ
- 引越し後に療育をスタートするためにやることリスト
これらについて説明します。
受け入れ可能な児童発達支援・放課後等デイサービス(療育)を探す
療育は、就学前か就学後かで利用できる事業所が異なります。
| 就学前 | ・児童発達支援センター ・児童発達支援事業所 |
| 就学後 | ・放課後等デイサービス |
就学前の事業所の探し方
就学前の療育については、
- 保育園や幼稚園を利用せずに児童発達支援のみ利用する
- 保育園や幼稚園を利用しながら児童発達支援も利用する
という2つのパターンがあります。
療育の利用の仕方に合わせて、センターや事業所を選びましょう。

ぼんちょは児童発達支援のみを利用する予定だったので、保育園や幼稚園のように給食・行事・クラス活動がある児童発達支援センターを希望しました。
引越し先の事業所情報の調べ方は次の方法があります
- 引越し先の自治体に相談してリストをもらう
- 引越し前に通っている療育の先生に相談してみる
- 相談支援事業所に相談する
- インターネットで調べる
最終的には必ず見学をしてから決めましょう。
就学後の事業所の探し方
就学後の療育は、放課後等デイサービスで受けられます。
放課後や長期休み期間の利用が考えられますので、引越し先の自宅や学校からの距離も考慮して選択しましょう。
受け入れてもらいやすいタイミング
児童発達支援・放課後等デイサービスには定員があります。
基本的には空きがあれば利用可能です。
ですがこれまでの経験上、ほとんどの事業所では次年度の4月に向けて利用者を決める時期が存在することが多いです。
児童発達支援では、4月に進級してクラス分けがあるような事業所だと前年度の秋頃〜12月ごろに受付の締切が存在する場合があります。
また、放課後等デイサービスだと支援学校までを含むすべての就学の決定が出る1月〜2月に次年度の利用者を決定する場合があります。
なので、これらの時期より前に事業所に相談できると次年度4月から受け入れてもらえる可能性が高まります。
引越しのタイミングがいつ決まるかにもよりますので難しい場合もありますが、引越しが決まったら早めに事業所に電話して相談しましょう。

ちなみにぼんちょの場合、11月に引越し先の児童発達支援センターに連絡をして見学。
1月に利用が決定しました。
もしすぐに空きがなかったらどうするのか
空きがなくてすぐに療育に通えない場合は、待機して空くまで待つことができる事業所もあります。ですが、空きを待っている間どこにも通えず家で過ごすのがもったいないと感じる場合は、「日中一時支援事業」を探してみるのも1つの選択肢です。
「日中一時支援事業」は次のような時に障害がある子を預かってくれる福祉サービスです
- 家族が仕事などで自宅に不在の時
- 家族に一時的な休息(レスパイト)が必要な時
療育ではありませんが、いろいろな活動をさせてくれ、子どもにとっても過ごせる場が増えるメリットがあります。

日中一時支援も住んでいる自治体ごとに利用できる時間・日数が異なります。
利用する場合は引っ越し先の自治体にルールを確認しましょう。
引っ越し先の療育の「通所受給者証」の手続きルールを調べる
先に大事なことをお伝えします。
療育の「通所受給者証」の運用ルールは市町村単位で全然違います!
引越しの際に療育の受給者証の手続きをする時は・・・
必ず引越し後の自治体の担当課に手続き方法を問い合わせましょう!
実はパトまめは失敗をしました。引越し前の担当課に1月ごろ手続き方法を聞いたんですね(引越しは4月)。

B市に引越すんですけど、療育の受給者証の手続きってどうなりますか?診断書とか提出するんですかね?
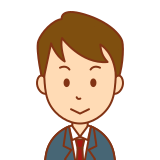
今のA市で使用している受給者証を転入する自治体に持っていけば発行できますよ。
・・・言われた方法ではダメでした!
引っ越し先の自治体役所へ別の用事で立ち寄った時に念のため確認したんですね。

今住んでいるA市に問い合わせたらA市の受給者証をB市に持っていけばB市の受給者証を発行できると聞いたんですけど・・・
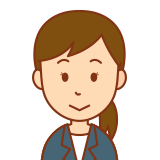
B市で受給者証を発行するには転入のお子さんについての診断書か意見書が必要です。
また、相談支援事業所を通して申し込むようになりますので事業所のリストをお渡ししますね。
聞いてたのと全然ちがうじゃん!(しかも相談支援って何?!)
そこから大慌てで・・・
- 受診して診断書を確保
- 相談支援事業所と契約
診断書は引っ越し前からお世話になっている病院で作成を依頼しました。
2月中にはどちらも完了しました。療育のための通所受給者証の申請には「障害児支援利用計画案」が必要です。
「障害児支援利用計画案」の作成には2通りの方法があります。
- セルフプラン(保護者や利用する児童発達支援事業所の支援者が作成する)
- 相談支援事業所に依頼する。
A市はセルフプランでの申請が可能であり、自治体や児童発達支援事業所の管理者にヒアリングしてもらいながら作成していました。なので相談支援事業所の存在すら、B市に引っ越すまで知りませんでした。
B市では必ず相談支援事業所に依頼して作成してもらってから療育を利用する流れが定められていました。
相談支援事業所については、自治体役所で相談すると事業所一覧がもらえるはずです。

保護者としての意見を言わせていただくと・・・
自治体ごとにルールが違うのわかりづらすぎるよ!
結論、最初に戻るのですが、
自治体ごとに手続きのルールが違いすぎるので、引っ越すときは必ず転入先へルールを確認しましょう。
療育の運用ルールは自治体ごとに異なる
引越しの時に驚愕したことは、療育を利用できる日数が自治体ごとに異なるということです。
幼稚園や保育園に通いながら児童発達支援に通う場合の利用日数のルールは次のとおりでした。
- 引越し前のA市では支援度に応じて月に13日・9日・5日
- 引越し前のB市では基本月に5日(支援度が高い場合に申請すれば8日)
なんでこんなに違うん!?
また、引越し前のA市では事業所の併用が可能なのにB市では併用不可でした。
だからなんでこんなにルールが違うん!?

引越しを経験して初めて自治体ごとのルールのちがいを知りました。
療育内容の引き継ぎ
引越し前に通っていた事業所での療育内容を引越し後の事業所に引き継ぐための準備をしましょう。
「個別支援計画」とその評価、事業所でのアセスメント結果がある場合はその内容を用意して伝えられるようにおきましょう。

ぼんちょは県内での引越しで距離的に可能とのことで引越し先の相談支援員さんが引越し前の事業所に引き継ぎを聞き取りに行ってくれました。感激しました。
引っ越し後に療育をスタートするためにやることリスト
引っ越し後に療育をスタートするためにやることについて「引越し前」と「引越し後」にやることをまとめます。
- 引越し先の自治体にある事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)を探す
- 引越し後の自治体役所に受給者証の手続き方法を確認
- 診断書や意見書が必要になる場合は主治医に依頼(引越し前の主治医でOK)
- 相談支援事業所を利用する場合は探して相談する
- 引越し先の自治体役所で受給者証発行の手続きをする
- 引越し前に使用していた受給者証を返還する
- 引越し前の事業所での療育内容を伝えられるよう準備する

すぐに事業所が見つからなかった場合は事業所が決まってから受給者証の手続きで大丈夫です。
手当や補助も手続きが必要!自治体が変わるともらえなくなることも・・・
「特別児童扶養手当」などの手当や補助も引越し先自治体での手続きが必要です。
手当や補助も自治体で定められたルールや基準があるため引越しで
- 支給されなくなる
- 金額が変わる
などの可能性があります。

ぼんちょの場合は引越し前の自治体では「日常生活用具給付」という制度でオムツへの補助が無かったのに引越し後の自治体では補助があるなど自治体ごとでのちがいがありました。
引越し先の自治体に障害福祉サービスをまとめた冊子がある場合は入手して制度のちがいを確認しておくことは大切です。
引っ越しで医療機関を転院する場合は?
次の流れで転院します。
- 引越し前の主治医に相談して医療機関を探す
- 紹介状をもらう
県内での引越しの場合は転院する必要がない場合もあります。
ぼんちょの場合も引越してしばらくは転院せずに片道50分かけて月2回の作業療法に通っていました。
ですが、作業療法を終了することになったのを機に自宅近くの小児神経科に転院しました。
引っ越し後の教育環境の準備は?

引っ越し後の地域で子どもに必要な教育環境をスムーズに整えるための準備についてまとめます。
就学前の教育環境の準備
就学前の教育環境の準備は次のとおりです。
- 保育園や幼稚園または毎日通える児童発達支援事業所を探す
- 見学・相談をする
- 入園の申請をする
保育園や幼稚園または毎日通える児童発達支援事業所を探す
就学前の子の引越し後の生活は次のパターンがあります。
- 保育園や幼稚園に毎日通う
- 通所支援事業所(児童発達支援事業所)に毎日通う
児童発達支援事業所に通う場合については先に説明しました。
保育園や幼稚園に通う場合もどんな園があるか引越し先の自治体で確認しましょう。
保育園や幼稚園を探す時に次のことについて情報収集しましょう。
- 保育園以外の預かり制度(幼稚園での預かりなど)があるか
- 障害がある子どもを受け入れるための枠を設定している園があるか
- 公立の幼稚園は基本的に学区の園に通うが学区外の園に選べる手段があるか
年度途中の引越し
保育園激選区
の場合は保育園に入れない可能性があります。
その場合、預かりがある幼稚園など別の手段があるかを確認しましょう。
また、他の選択肢として幼稚園の後に
療育
日中一時支援
に子どもを預けて働くという方法もあります。

ただし利用できる日数が自治体によって違うため要確認。
また幼稚園から事業所までの送迎方法(事業所が送迎できるか・ファミサポを使用できるか)も要確認です。
お子さんに障害がある場合、親としては過ごす環境に頭を悩ませます。地域によっては障害があるお子さんを受け入れるための枠を設定している園がある場合もあるため引越し先の園情報を確認しておきましょう。
また、公立幼稚園に通う予定の場合は、学区以外の幼稚園の選択肢があるかどうかも情報収集しておきましょう。
自治体によっては人数が少ない園や特色ある教育をしている公立幼稚園には学区外からでも通えることがあります。

ぼんちょが住んでいる地域は学区外から通える公立園がありました。
学区の園がマンモスで人数多い場合には検討しても良いかもしれません。
見学・相談をする
入園を希望する園の候補が絞れたらできる限り見学をしましょう。現場の雰囲気や支援体制は見てみないとわかりません(見てもわからない時もあるけど・・・)。
また、我が子の
- 障害の内容
- 必要な支援
について説明して受け入れ可能かどうかの相談をしましょう。

特に私立園は園ごとに特色がちがうなと・・・保育園探しの時に感じました。
入園の申請をする
特に注意したいことは
申請期限です。
申請期限には
- 次年度4月入園を希望する場合の申請期限
- 年度途中で入園を希望する場合の申請期限
が定められているはずですので引越し先の地域の申請時期を確認しておきましょう。
就学後の教育環境の準備
就学後(おもに小学生)の教育環境の準備は次のとおりです。
- 学校の情報を集める
- 見学・相談をする
- 転校の申請をする

転校だけでなく引越しと就学のタイミングが重なる場合も参考にしてみてください。
学校の情報を集める
- 小学校(通常学級/特別支援学級/情緒支援学級など)
- 特別支援学校
どちらに通うとしても学校の情報を集めるのは大事です。
引越し後の住む場所が決まっている場合は、小学校も特別支援学校も通える学校が学区で定められているはずです。
ただし小学校の場合は、通いたい学級が学区の学校に無いこともあり得ます。
その場合は引越し先の教育委員会に相談しましょう。
- 必要な学級を新設
- 学区外の小学校へ通う
などが認められる可能性があります。
また、通常学級に通うとしても幼稚園と同じように学区外の小学校に通える可能性もあるため自治体に確認しましょう。

ぼんちょが住む地域では自治体から指定されている特色ある教育をしている小学校や過疎地域の小学校には申請すれば学区外から通えるよ。学びたい内容がある場合や少人数で学ぶ方が向いているお子さんが希望して学区外に通うことがあります。
特別支援学校についても、
- 県立支援学校
- 市立支援学校
- 大学附属の支援学校
- 寄宿舎付きの支援学校
など地域によっては複数選択肢があることもあるので情報収集しましょう。もしも引越し後の住む場所が自由に選べる場合は学校の選択肢が増えます。
その場合は引越し前に見学して学校を決めてから住居を決めることをおすすめします。
学校が決まったら、学校からの距離がなるべく近い場所に住居を用意できると通学の負担も軽減できます。

そんな都合よくちょうど良い位置に住む場所が見つかることは稀ですけどね・・・
見学・相談をする
引越し後に入学・転校を希望する園の候補が絞れたらできる限り見学をしましょう。
特に小学校はクラスごとの人数や学校全体の生徒数などで学校の雰囲気がだいぶ変わります。
また引越しのタイミングと就学のタイミングが重なって学級や学校選択に悩んでいる場合は、お子さんの
- 障害の内容
- 必要な支援
について伝えた上で対応可能な支援を確認したり就学選択の希望を伝えましょう。
重度知的障害の子の学校選択や小学校入学前におすすめの書籍についてまとめたこちらの記事もどうぞ↓

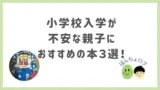
転校の申請をする
転校の申請の前に転校が決まったら次のことをしましょう。
- 通っている学校に転校を伝える
- 引越し先の自治体役所に手続き方法(必要書類など)を確認
転校の手続き自体は、
- 転出届をもともと住んでいる自治体の役場に提出
- 転入届を引越し先自治体の役場に提出
が終わってから行います。
前の教育環境から次の教育環境への引き継ぎ
引越し前に通っていた園や学校がある場合は、担任の先生にお願いすると引き継ぎ内容を書面で用意してもらえる場合があります。
集団生活の中での
- 困り感
- 有効だった支援
などは担任の先生が一番わかっています。
用意してもらえそうだったらお願いしてみましょう。

ちなみにぼんちょがいた保育園は、ぼんちょだけでなくぼんちょ兄の分まで準備してくれました。
新しい環境に慣れるために子どもと一緒に足を運ぶ
引越しが都道府県をまたぐ場合には引越し前には子どもと一緒に引越し先の園や学校に見学に行くのが難しい場合もあります。
もしも引越し後に転園・転校初日までに時間がある場合には、なるべく子どもと一緒に園や学校へ行くことをおすすめします。子どもにとって環境が変わるのはとても負担があることです。
実際に足を運んで先生と事前に会うことで不安が軽減できることもあります。
お願いして降園後や放課後に園庭や校庭の遊具で遊ばせてもらうこともおすすめです。

ぼんちょ兄は引っ越し前に園庭開放におじゃまし、園庭で遊ばせてもらう機会がありました。
好きな遊びが見つかって少しだけ新しい園に行く不安が和らいだようでした。
まとめ
障害児がいる家族の引越し手続きについて、注意すべき点とやるべきことをブログでまとめました。
障害児と家族の引越しでは次のことが大切です。
- 事前準備
- 情報収集
- 情報の引き継ぎ
- 子どもが過ごす環境を整える
障害福祉制度の運用や手続きが自治体ごとに異なるので、引越しが決まったら早めに手続きが必要な制度をリストアップして必要な書類などの準備物の用意に取りかかりましょう。
引越しに関係する手続きすべてにおいて、引越し前の自治体だけでなく引越し後の自治体に確認することを強くおすすめします。
また、これまで受けてきた支援についての情報の引き継ぎも大切です。
情報が途切れてしまわないように気をつけましょう。
子どもが過ごす新しい環境を探す際にも、情報収集は欠かせません。
子どもの障害の内容や必要な支援を整理して可能な限り合う環境を探しましょう。
また、過ごす場所が決まったらお子さんと実際に足を運ぶことで不安が軽減できるかもしれません。
今回は、実際に引っ越しを経験した経験をもとに、障害児と家族が一緒に引っ越す際に知っておくと良い情報をまとめてみました。これから引越しをする人に、何か参考になることがあれば幸いです。
もし、この記事を読んで足りないことやお気づきの点がありましたら、お問い合わせやXのDMでご連絡くださると嬉しいです。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!