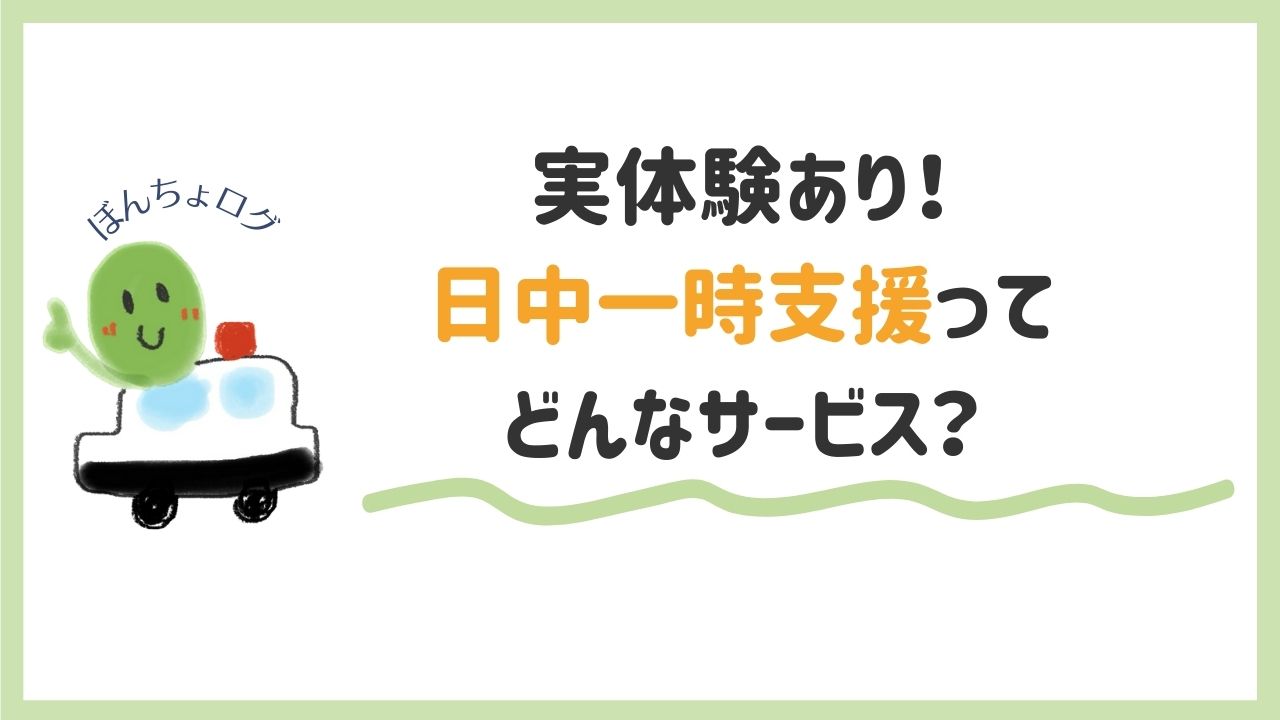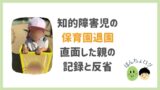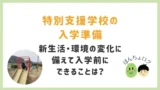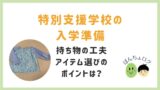重度知的障害児「ぼんちょ」がたくさんお世話になっている「日中一時支援」という障害福祉サービスについてブログで紹介します。

放課後はもちろん夏休みなどの長期休みにもたっぷりお世話になっています。
重度知的障害児ぼんちょも利用している日中一時支援について、どんなサービスか・どんな利用の仕方が可能なのか・選び方のポイントについて、実際の体験をもとにブログにまとめます。
日中一時支援は、障がいのあるお子さんや療育を利用しているお子さんが日中に安心して過ごせる福祉サービスです。
「どんな活動をさせてくれるの?」
「安全面は大丈夫?」
「子どもが楽しく通える?」
日中一時支援の事業所を複数利用しているぼんちょの経験から
- 日中一時支援って何?
- 実際に日中一時支援を利用した経験談
をお話した上で、選び方のポイントを紹介します。→ポイントをすぐに知りたい人はジャンプ
おもに未就学児・小学生の保護者向けにわかりやすく紹介します。
日中一時支援って何?
日中一時支援を利用していない人にとっては何をしてくれるところなのかよくわからないですよね。
私も日中一時支援という福祉サービス自体・・・
ずっと知りませんでした!!!
利用していない人には是非使って!とおすすめしたいのでくわしく説明します。
日中一時支援って何をしてもらえるの?
日中一時支援では、障害がある子(人)や支援が必要とされる子に対して次のことをすると決められています。
厚生労働省HP「地域生活支援事業等の実施について」より引用
- 安心して過ごせる活動の場を提供
- 活動の見守り
- 社会に適応するための日常的な訓練
- その他市町村が必要と認める支援

要するに障害がある子(人)が活動ができる自宅以外の場所ってことです。
「それって療育とは何がちがうの?」という疑問には次の「日中一時支援事業の目的は?」で説明します。
日中一時支援事業の目的は?療育とは何がちがうの?併用は?
まず最初に、日中一時支援事業と療育は併用ができます!
どちらも障害のある子どもが活動する場所ということで勘違いされることもありますが併用できます。
日中一時支援事業の目的は次のとおりです。
厚生労働省HP「地域生活支援事業等の実施について」より引用
- 障害のある子(人)の家族の就労支援
- 日常的に介護している家族の一時的な休息(レスパイト)
このとおり日中一時支援事業の目的は「家族」に焦点が当たっています。
一方療育(児童デイサービス事業)の目的はどうかというと、
厚生労働省HP「児童発達支援ガイドライン」より引用
- 子どもの障害の状態や発達の過程・特性に配慮しながら子どもの成長を支援
- 日常生活や社会生活の向上に必要な支援を行い、子どもの自尊心や主体性を育てつつ発達上の課題を達成させる
このとおり療育の目的は「子ども」に焦点が当てられています。
障がいのある子どもの発達支援や社会性の向上を目的として、継続的なプログラムを提供されるのが療育です。
このような目的のちがいから、日中一時支援は
「家族の生活への直接的支援」が目的とされている事業だと捉えて私は利用しています。

もちろん療育でも子どもの課題が達成されていくことで家族が助かるという側面はあります。
また最近では療育でも親の就業によって利用時間が長くならざるを得ない場合の預かりニーズから「延長支援加算」の見直しが行われました。
(参考:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について」
日中一時支援は誰が利用できるの?
厚生労働省HP「日中一時支援の概要」では「障害者等」と記載があります。
なので障害者であることを示す障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っている場合は利用できます。
その他、実施主体は市町村ということで、自治体ごとに要綱で決められています。
このうちどれかに該当する場合に利用を認めている自治体があります。
また、利用年齢は65歳までの人が利用できますが事業所ごとに利用できる年齢が定められていることがほとんどです。

ぼんちょが利用している事業所は18歳までが対象です。
だからそれ以降は改めて他の事業所を探す予定です。
利用料金はどれくらいかかる?
日中一時支援の利用料金についても各自治体ごとに定められています。
共通しているのは、利用料金の1割のみを家庭で自己負担するということです。
また利用料金については障害の状態によって金額の区分が定められている場合があります。

1時間100円ちょっとの負担で利用できてしまうんです。
本当にありがたいです。この気持ちを常に持っていたいと思います。
利用できる1ヶ月あたりの日数や時間数は?
利用できる量についても各自治体ごとに決められています。
共通しているのは、保護者が両親とも働いていれば週5をカバーできる日数が支給されています。
ですが、最初に目的を説明したように日中一時支援事業の目的には、障害児の介護に携わる家族の一時的休息(レスパイト)の側面があります。
なので、片方の親が働いていないとしても自治体で決められた日数(時間数)利用することができます。
実際に日中一時支援を利用した経験談①
ぼんちょは現在2ヶ所の日中一時支援の事業所を利用しています。
利用のきっかけは保育園を辞めて仕事を退職した後に利用を始めた児童発達支援センターで出会った保護者から教えてもらったことでした。

正直仕事を辞める前に日中一時支援の存在を知っていたら仕事を辞めずに済んだ可能性すらあります。
実際に日中一時支援を利用した経験談をお話します。
日中一時支援事業所(事業所A)を選んだ決め手
ぼんちょが1つ目に利用を開始した日中一時支援事業所(事業所A)の特徴を紹介します。
事業所Aの特徴は次のとおりです。
| 利用開始時期 | ぼんちょが3歳の時 |
| 場所 | 自宅と児童発達支援センターから近い |
| 対象年齢 | 未就学児〜18歳 |
| 開所時間 | 8時00分〜20時00分 |
| 昼食 | 調理して提供あり(持ち込みも可) |
| 送迎 | あり |
| 職員 | 女性ばかり |
| 利用日時の決定 | 基本は利用する曜日を固定して、空いていれば他の曜日にも利用できる。 |
| 活動内容 | 室内遊び・外遊び・宿題(宿題がある子)・季節の制作やイベント |
事業所Aは、児童発達支援センター入園後だいぶ慣れた時に利用し始めました。
この事業所にした一番の決め手は
同じ児童発達支援センターの利用者が多かったこと。
口コミを聞いて見学すると、管理者の先生がしっかりしていてフィーリングが合ったのでそのまま契約。

地域の保護者からの情報が背中を押してくれて見学・契約まであっという間でした。
日中一時支援事業所(事業所A)を利用して良かったこと
事業所Aは3歳からすでに4年以上利用しています。
利用してみて良かったことを紹介します。
- 朝早くから夜遅くまで利用できる。
- 事業所内に屋外で遊べるスペースがある。
- 子どもたちが過ごしやすいように室内や屋外の環境整備をしてくれる。
- 昼食は希望したら事業所内で給食を出してくれる。
- 連絡帳がある(毎回利用時の様子について記入あり)
- 同じ地域に住んでいる子の利用が多い
朝早くから遅くまでの開所はきょうだい児の予定がある時にとても助かった
土曜日の朝早くにぼんちょ兄の学校行事がある時に預けることができるのは本当に助かりました。
また、ぼんちょは一時期夜ごはんを持って利用していました。
夜にあるぼんちょ兄の習い事に付き添う日に、夜ごはん(お弁当)を持たせてお願いすると食べさせてくれました。

開所時間が朝早くから遅くまでの事業所だと、予定に合わせて利用しやすく助かります。
外遊びしやすい環境
事業所Aには敷地内に屋外で遊べるスペースがあります。
屋外で遊ぶのが好きなぼんちょにとってはとてもありがたい環境です。
しかも屋外スペースは柵で囲って安全対策もバッチリです。
環境整備で過ごしやすくなるよう対策されている
事業所Aはワンフロアの平屋です。
固定パーテーションで活動場所を区切り、次のようなことを防ぐためにゾーンを分ける環境の工夫がありました。
- 身体が大きかったり動きの多い子どもとそうではない子がぶつかるのを防ぐ
- 室内で走り回るのを防ぐ
なんと室内だけでなく屋外の遊び場まで小さい子のゾーンを区切ってあるのには度肝を抜かれました。
工夫された環境整備を見て、
「この事業所だったら年齢が大きくなっても安全に利用できるかも」と思えます。

親としては我が子の身体が大きくなってくると、安全上小さい子どもがいる事業所で過ごすことが気になり始めます。
土曜日や夏休みにお弁当を作らなくても良い
ありがたすぎて涙が出ます。
もちろん自分で持って行くこともできます。
なかなか無いです、昼食を作って提供してくれる事業所。
活動の様子を毎回連絡帳に書いてくれる
何をして過ごしたのか、親としては気になりますよね。
日中一時支援では連絡帳は義務では無いのですが、連絡帳があると親としては情報共有しやすくありがたいです。
地域の小学校に通っている子と交流できる
ぼんちょは特別支援学校に進学しました。
さらに放課後等デイサービスも支援学校の子どもが対象の事業所を利用しています。
なので、ぼんちょにとっては日中一時支援が唯一地域の小学生と交流できる場になっています。
支援学校では大人からの関わりや声かけが多い生活になります。
一方、日中一時支援では地域の小学校に通っている同年代の子どもからの関わりや声かけがあります。
唯一地域の子どもたちとしっかり関わってもらえる場所なので、今後もぼんちょの活動場所として大切にしていきたいです。

たまに住んでいる市内で「ぼんちょくん!」と声をかけられることがあります。
ほとんどがここの日中一時支援で関わりがある子です。
住んでいる地域の子どもたちにぼんちょの存在を知ってもらえることが、親としては嬉しいです。
実際に日中一時支援を利用した経験談②
ぼんちょが年長の時に、小学生には長期休みがあるということに気づきました。

僕が通っていた児童発達支援センターの連休はGWとお盆、年末年始くらいでした。
ぼんちょが住んでいる自治体では、夏休みの7月と8月は毎日利用できるくらい利用日数を増やすことが可能と知りました。そこで、

せっかくだから毎日同じ事業所を利用するのではなく、もう1カ所契約して交互に利用してみようか・・・
と考えて、小学1年生の夏休みに向けて新たに事業所を探すことになりました。
日中一時支援事業所(事業所B)を選んだ決め手
ぼんちょが2つ目に利用を開始した日中一時支援事業所(事業所B)の特徴を紹介します。
事業所Bの特徴は次のとおりです。
| 利用開始時期 | ぼんちょが年長の12月 |
| 場所 | 進学予定の支援学校に近い |
| 対象年齢 | 未就学児〜18歳 |
| 開所時間 | 9時00分〜18時00分 |
| 昼食 | 弁当持参(仕出し弁当の注文も可) |
| 送迎 | あり |
| 職員 | 男性・女性両方 |
| 利用日時の決定 | 前月中旬までに申請すれば基本いつでも利用できる |
| 活動内容 | 室内遊び・外出(公園や散歩)・宿題(宿題がある子)・季節の制作やクッキング、遠足イベント |
事業所Bは、支援学校に入学する前の年長12月から利用し始めました。
この事業所にした一番の決め手は、
支援学校に近かったこと!
事業所Bは外あそびをするためには公園に行く必要がありました。
行くとなると事業所から近い公園(つまり支援学校から近い公園)に行きます。
ぼんちょが進学する支援学校は住んでいる地域から離れていてあまり馴染みのない土地でした。
なので、入学前に学校がある地域に慣れるといいなという気持ちがありました。

だから入学前に余裕を持って利用を始めました。
支援学校から近いため利用者も支援学校の子が比較的多かったです。
夏休みなどの長期休み中に同じ学校の子に会えるのもいいなと思い、支援学校近くの事業所を利用することに決めました。
支援学校への入学準備の記事はこちらをどうぞ↓
日中一時支援事業所(事業所B)を利用して良かったこと
事業所Bは年長の12月から1年以上利用しています。
利用してみて良かったことを紹介します。
- 利用日追加の融通が利きやすい
- 色々な場所に連れて行ってくれる
- 行事が多い
- 連絡帳がある(毎回ではないけど写真付き)
- 送迎時に職員としっかり話ができる
急な用事で追加したい時やイレギュラーに対応してくれる
利用希望は前月の中旬に提出することになっていますが、
「急な予定が入った時などは相談してください」
と言ってくれていました。
「急な予定が入ることもある」こと事業所側が想定してくれていることに利用児の家族への思いやりをすごく感じます。

基本予定を変えて利用することはありませんが、それでも緊急時はあるかもしれないのでありがたいことです。
家族で行ったことのない公園に連れて行ってくれ、楽しめる場所が増えた
事業所Bは近隣の公園情報にとても詳しく、

ぼんちょ君好きそうだなと思って今日は◯◯公園に行ってみました〜
と報告を受ける日も多いです。
家族では行ったことのない公園だったことも多いです。
楽しめた公園を報告してもらうことで家族でのお出かけ先のレパートリーが増えました。
クッキングや遠足などの行事がある
土日や長期休みにクッキングや遠足があります。
日中一時支援のクッキングでは、作業の中のできそうな工程を担当します。
ぼんちょも今までに芋をつぶす、型抜きなどを担当しました。
また、遠足ではトランポリン施設や市外の公園などに行きました。
支援学校の先生から
「ぼんちょ君は普段からいろんなことを経験しているからか新しいことを受け入れやすい」
と言われました。
日中一時支援での活動のおかげかもしれません。
連絡帳に写真の記録が残るのは嬉しい
B事業所の連絡帳は毎回のやりとりではないのですが、時々写真を貼ってくれます。
文字だけの連絡帳もありがいのですが、写真があるとより活動の様子がわかりやすいです。

子どもたちに楽しく活動させてくれるだけでもありがたいのに、それを記録として写真に残してくれるなんて神すぎる・・・!
送迎時の対応が信頼できる
B事業所は自宅から距離があるため送迎を事業所にお願いしています。
実は私が一番B事業所を信頼できる事業所だと感じたのは送迎時の対応。
事業所の職員から

今日実はこんなことがあったんですけど
おうちでもありますか?
そういう時どんな対応していますか?
と、ちょっとしたことでも尋ねてくれるんですね。
少しても気になったことは保護者に確認する、その姿勢に
信頼できるな〜
と感じました。
家でも同じようなことがある場合は、対応を伝えて事業所でも同じように接してもらえるよう話し合うこともできました。
保護者としても事業所で起きたことは良いことも悪いことも知らせてもらえるとありがたいです。
報告・連絡・相談のいわゆる「報・連・相」がしっかりしている事業所は安心感があります。
日中一時支援事業所を選ぶ時のポイント
これまでに日中一時支援事業所を見学したり利用したりした経験から、日中一時支援事業所を選ぶ時のポイントについて紹介します。
1. 立地・アクセスのよさ
- 自宅や学校・園から近い場所にあると送迎や移動の負担が少ない。
- 進学予定の学校が慣れない地域にある場合は学校生活に向けて、地域に慣れるための利用もおすすめ。
2. 開所時間と柔軟な利用体制
- 朝早くから夜遅くまで開いていると、保護者やきょうだいの習い事の予定に合わせやすい。
- 急な予定に対応してくれるなど、融通が利くかどうかもチェックポイント。
3. 食事の提供の有無
- 昼食を用意してくれる事業所はとても助かる。
- 弁当の持ち込み以外にも仕出し弁当など外注の選択肢があると便利。
4. 送迎サービスの有無と対応の丁寧さ
- 送迎があると移動手段が限られる家庭でも利用しやすい。
- 送迎時に子どもの様子を丁寧に伝えてくれる職員だと、安心して預けられる。
5. 職員との相性・対応の良さ
- 管理者や職員とのフィーリングが合うかも大切。
- 日々の報告や相談がしやすいと、信頼して任せられる。
6. 活動内容の充実度
- 屋内外での遊び、宿題サポート、制作やクッキングなど、活動が多彩かを確認。
7. 安全に配慮された環境
- 安全な環境整備(特性や年齢でゾーンを仕切っている・安全のための柵など)がされていると、年齢や特性に応じて安心して過ごせる。
8. 地域の子どもたちとの交流
- 地域の小学生などと関われる場所は、社会性を育む場としても貴重。
- 特に支援学校に行っている場合は住んでいる地域の子に存在を知ってもらえる機会。
8. 情報共有の方法(連絡帳など)
- 連絡帳があると安心。活動の様子が詳しくわかる。
- 写真付きの記録があると、よりわかりやすいし思い出としても残せる。

なかなかすべてを満たす事業所を見つけるのは難しいかもしれません。
そういう時は優先順位を決めて探してみることをお勧めします。
まとめ
重度知的障害児ぼんちょも利用している日中一時支援について、どんなサービスか・どんな利用の仕方が可能なのか・選び方のポイントについて、実際の体験をもとにブログにまとめました。
日中一時支援は、障がいのあるお子さんや療育を受けているお子さんが自宅以外でも安心して過ごせる時間と場所を提供してくれる大切な福祉サービスです。
この記事では、我が家の実際の体験をもとに「日中一時支援とは何か?」という基本から利用するメリット・選び方のポイントまで、未就学児・小学生の保護者の方にもわかりやすく紹介しました。
事業所によって特色や雰囲気はさまざま。だからこそ、見学や情報収集を通じて、お子さんの特性やご家庭の状況に合った事業所を選ぶことがとても大切です。
そして何より、この支援が「親の働き方」や「家族の生活の質」にも深く関わっていることを、私自身の経験から強く感じています。
「仕事を続けたかったけれど難しかった」
「もっと早くこの制度を知っていれば…」
そんな思いをするご家庭が少しでも減るように、この記事が参考になれば嬉しいです。
ぜひ、お住まいの自治体の制度を調べて、見学や相談から一歩踏み出してみてください。
日中一時支援を上手に活用して、子どもにとっても家族にとっても、安心できる居場所や時間が増えていきますように。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!