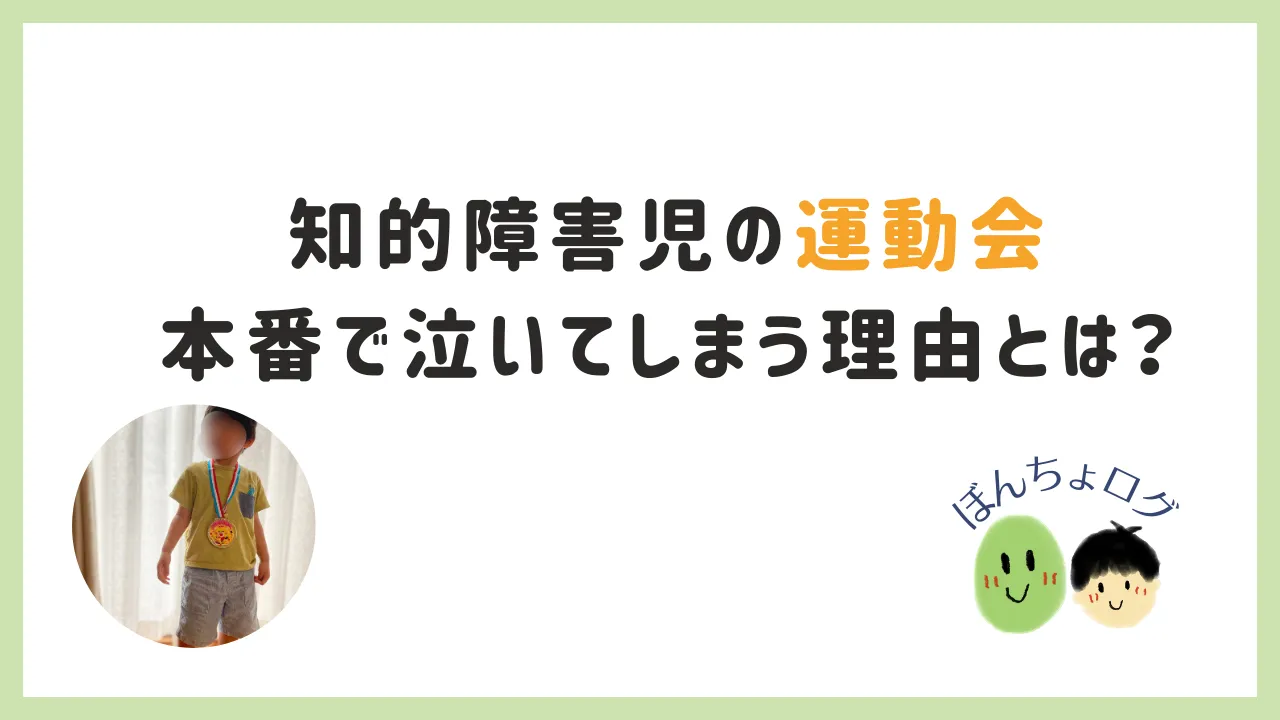ぼんちょは4年間通った児童発達支援センターで4回の運動会を経験しています。
知的障害や発達障害がある子どもにとって日常生活とは違う行事である「運動会」は苦手なお子さんも多いです。
今回はそんな「運動会」について、重度知的障害ぼんちょのこれまでの経験や運動会に向けて親としてやったみたことなどを紹介します。
知的障害児と運動会に向き合う親の悩み

練習中はできているのに本番はうまくいかない
児童発達支援センターの運動会は秋(10月)でした。
練習は夏のプールが終了したらすぐに開始します。
本番前になると連絡帳に先生が運動会の練習の様子を記載してくれることも多く、
「できました」
「がんばりました」
という記載が増えます。
ところが本番になると、ぼんちょは競技中も出番を待つ時間も泣く時間が多いということが2年続きました。
運動会本番がうまくいかない理由
- たくさんの人が集まっていて刺激が多い環境
- 親が見えると親のところに行きたくなる
ぼんちょの場合はこの2つが理由でした。
いくら練習でうまくいっても練習と本番の環境の落差が大きいのが運動会。
周りにたくさんの保護者がいるだけでも子どもによってはびっくりしますよね。
そしてそこに親が見つかったとなると安心のために駆け寄りたくなるのは当然と言えば当然です。
運動会本番での親の立ち回り方

子どもから親が見えないように工夫する
- 人混みにまぎれる
- 人や遊具などの後ろに隠れる
親が見えたら泣いてしまうのであれば
親は隠れる!
これは有効な1つの方法です。
運動会なので、声援を送って応援したい気持ちもわかります・・・
ですが、本人が集中して運動会の競技に取り組むことを重視するのであれば気配を消して心の中で応援するのも1つの方法であり大事な環境設定です。

3回目の運動会で隠れる方法を試しました。これまでで最も競技に参加することができました。それ以降、発表会でもぼんちょから見えない場所から見守るというスタンスを貫いています。
当日の親の動きについて事前に先生とも相談しておく

- 運動会のスケジュールを教えてもらう
- 親がどこまで隠れるか決めておく
事前に運動会のスケジュールを親も知っておくことは大切です。
親子競技がある場合は親と対面する必要がありますので、どこまで隠れてどのタイミングで親の存在を子ども明らかにするか打ち合わせしておきましょう。
実際の体験談:先生からのサポートや親として学んだこと
子どもの特性に合ったサポート
- 個々ができることを大切にした競技
- 「待つ」時間の工夫
ぼんちょが通っていた児童発達支援センターでの運動プログラムはこんな感じでした。
- スケジュールの確認
- 入場・準備体操
- かけっこ(走ってマッチングして折り返して帰ってくる)
- お楽しみ競技(障害物を超えてボールなどをプットインしてゴール)
- 親子体操
- 閉会・メダル贈呈
普段の療育でしていることを取り入れた競技構成でした。
お楽しみ競技では「くぐる」「登って降りる」などの障害物が用意されていましたが、それぞれに合わせてコースが選べる構成でした。
また自分の番を待つ間は椅子と机が用意されていて、応援して待つのが難しい子どもはお気に入りのグッズで遊びながら待つこともできました。
運動会開始前に、みんなでスケジュールの確認をするのも児童発達支援センターならではかも知れませんが、先の見通しがある方が安心できる子には必要な支援です。
本番でうまくいかなくても練習で頑張ったことを褒めたい
ぼんちょは本番で練習どおりうまくいくことはあまりありませんでした。
児童発達支援センターの良いところは、
- 本番までにたくさん練習をしてくれる
- 練習の様子を親に伝えてくれる
ところです。
本番でうまくいかなくても、練習で繰り返し取り組んだことも必ず子どもの力になっています。
親としては、本番がうまくいかなかったとしても「今日までよく頑張ったね。今日運動会に来れただけでも花丸だよ。」と言ってあげたいです。
また、ぼんちょの児童発達支援センターでは練習中の動画や写真も残してくれていて後日もらうことができました。
保護者にとってはとてもありがたい配慮です。
まとめ
運動会は知的障害や発達障害のある子どもにとって特別な挑戦です。環境の変化や刺激の多い状況が負担になることもありますが、練習や本番を通じて親子共に成長する機会でもあります。
練習でできていても、本番では環境や状況の違いからうまくいかないことがあるのは自然なことです。
特に親が見えてしまうと泣いてしまった競技に集中できないという場合には、親が隠れるなど子どもが集中しやすい環境を整えるなど事前に先生としながら工夫していくことも方法の1つです。
子どものペースや特性に合わせた競技プログラムや「待つ」時間の支援などが知的障害の子どもが運動会に参加するためには必要です。
先生から練習の様子を共有してもらいながら、親子ともに本番に備えていけると安心です。
本番の結果にこだわらず、練習を頑張ったことや運動会に参加できたことをまず親子で喜べると良いですね。経験の積み重ねが子どもの成長につながります。
知的障害児の運動会は親として悩みや不安が大きいかもしれません。
ですが、工夫次第で親子にとって意味のある経験に変えることもできます。
運動会に同じような心配事を抱えているご家庭に少しでも参考になれば幸いです。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!