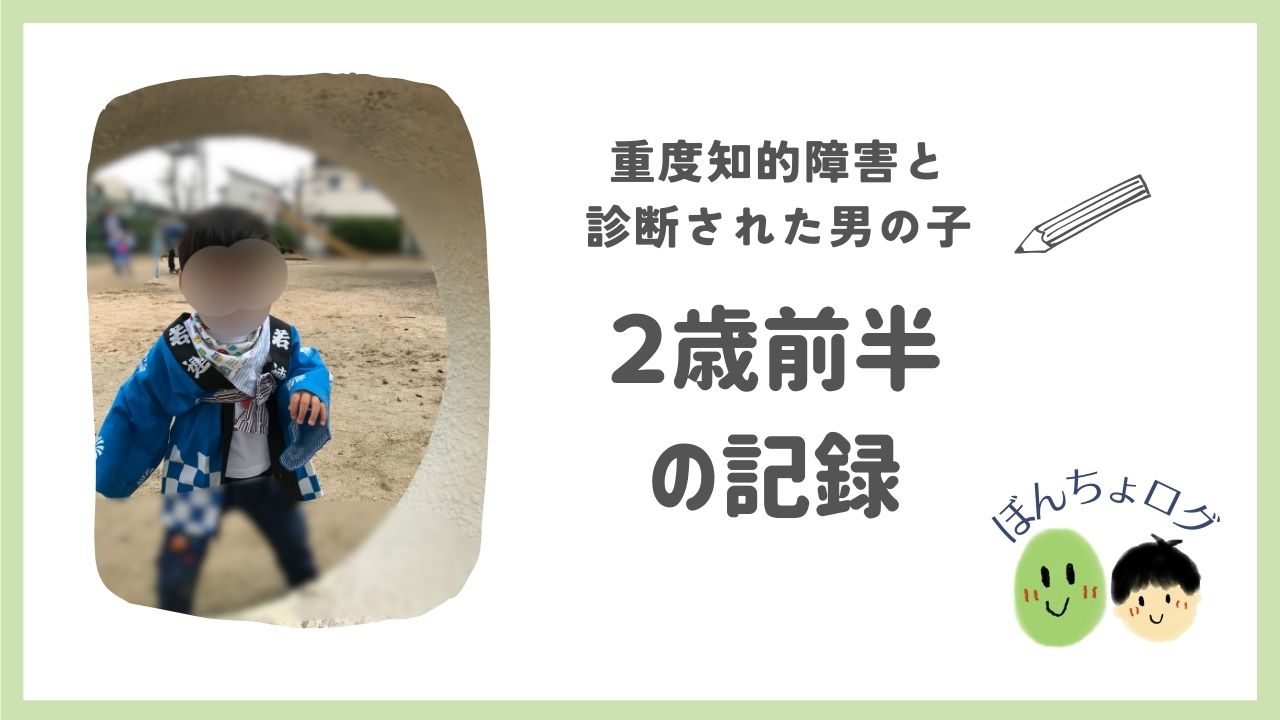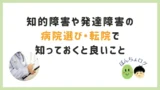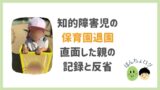重度知的障害と診断された「ぼんちょ」が2歳の時の様子を紹介します!

2歳は保育園に通いながら作業療法や療育に通い始めた時期。発達検査も受けたよ!

重度知的障害児「ぼんちょ」の2歳児の頃の特徴や成長の記録をブログにまとめます。
ここに書いてある2歳児の頃の成長記録がすべての知的障害の子どもに当てはまるわけではありません。
ひとりの重度知的障害の男の子の過去の記録として誰かの参考になれば幸いです。
2歳児の頃の特徴の前に!1歳時期のおさらい〜大学病院の初受診をした時期でした
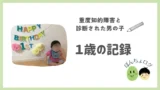
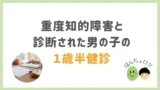

1歳ですでに波瀾万丈ですね。それでは、2歳の成長や出来事を紹介していきます。
重度知的障害と診断された子の2歳から2歳6ヶ月までの発達は?|意思表示が出始めたけど困難さも増した時期
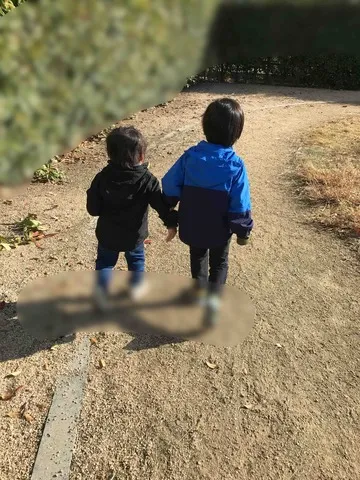
重度知的障害とのちに診断される「ぼんちょ」の2歳児の頃の発達の記録をブログにまとめていきます。
結論から言うと、2歳台は要求や否定など意思表示が出始めた時期でした。
ところがそれを言葉では伝えられないため動作や問題行動で表現していました。
そんな重度知的障害児ぼんちょの2歳当時の成長記録をまとめます。
2歳では要求(クレーン現象)や否定など意思表示が増えた
重度知的障害とのちに診断される「ぼんちょ」は、2歳になってから「してほしいこと」がある時に相手の手を引いて伝えることが増えました。
大人の手をとって自分のしてほしいことや要求を叶えようとすることを「クレーン現象」と呼びます。
インターネットで「クレーン現象」と検索すると自閉症の子どもによく見られるといった検索結果が出てくることもあります。(ですが言葉が使えない時期に思いを伝える手段としてやっていることなので、自閉症と診断される子以外にも見られてもおかしくはありません。)
また、ぼんちょは反対に何かをしたくない時には身体を張って拒否するようになりました。
具体的には、移動したくない時に、手を繋いでいても力を抜いて座り込んで動かなくなりました。
人なので要求や否定はあって当然です。成長したとも言えます。
ですが、家族としては日常生活で次のような困難さが増しました。
- 子ども本人に伝える手段が少ないために親としてすべての気持ちをわかってあげられない
- 身体を張って要求を叶えようとしたり拒否したりされるため対応がしんどい
意思表示が出始めて成長を感じる反面、家族としての悩みは増え始めました。
短い言葉(単語)を理解できるようになった
重度知的障害とのちに診断される「ぼんちょ」ですが、2歳ごろに「ご飯」「お風呂」などの短い単語を理解して動けるようになりました。
次の活動に誘う時には短い言葉で話しかけるよう心がけていました。それが良かったのか、いつの間にか日常生活で毎日使われる単語を聞くと自分から活動をする場所に移動することが増えました。
ぼんちょ兄と比べると大人が話す言葉を理解する力がないと感じていたため、成長が感じられたことはとても嬉しかったです。
おもちゃや遊びなどの興味の広がったが、こだわりが出てきた
重度知的障害とのちに診断される「ぼんちょ」は2歳からの半年間で、次のようなおもちゃで少しずつ遊ぶようになりました。
- 磁石でくっつくおもちゃ
- 簡単なブロック
- コップ重ね
作業療法に行き始めてさまざまなおもちゃを触らせてもらえたことも興味が広がった1つの理由かもしれません。
ですが、次のような特定のものへのこだわりや遊び方のマイルールも見られるようになりました。
- 外では草や葉っぱばかり触って遊ぶ
- ボビンを紐に通したものをひたすら振って遊ぶ
- クレヨンや鉛筆など筆記用具を見ると触らずにはいられない
- 投げてはいけないものを投げて感覚を楽しむ
- 自分で思いついた遊び方で遊びたい
新しいおもちゃに興味が持てても自分で面白いと思った感覚にこだわってしまうため
- おもちゃの本来の使い方で遊べない
- 危ない行動につながってしまう
といったことが、新たなぼんちょの困りごとして追加されました。
2歳からスタートした発達の遅れへの支援|発達検査・作業療法・療育
重度知的障害とのちに診断される「ぼんちょ」は1歳で大学病院へかかり2歳から発達への支援が受けられるようになりました。
2歳で初めて受けた新版K式発達検査と診断結果
重度知的障害児「ぼんちょ」は2歳の頃、大学病院小児神経科の主治医と相談をして作業療法を受けることになりました。作業療法を開始する前に、ぼんちょの発達段階を明らかにするために「新版K式発達検査」を受けました。
受けたといっても、ほとんど何もできず・・・だったんですけどね(汗)
初めての「新版K式発達検査」(2歳2ヶ月の時)の結果、
DQの数値から「中等度発達遅滞」という診断がつきました。
つまりこの検査によって、ぼんちょは知的障害だと初めて診断されました。

ここまで入院でMRIやら染色体検査やら色々してきていたのもあって、「知的障害」だということは「発達検査を受けて診断を受ける前からわかっていた」というのが本当の気持ち・・・
この時には、実はショックよりも「そりゃそうですよね」という気持ちが大きかったです。
2歳からスタートした作業療法
2歳になって病院での作業療法をスタートしました。ぼんちょは毎月2回、2歳1ヶ月から3歳4ヶ月まで病院で作業療法を受けました。
作業療法士のもとでは、次のようなことをしてもらいました。
- トランポリンやシーツブランコ、台車などを使って感覚のチェック
- 興味のあるおもちゃを探ってもらい、手の操作を観察
作業療法を受けてよかったことは次のとおりです。
- 好きな感覚と苦手な感覚がわかったこと
- おもちゃの遊び方のくせなどを見つけてもらったこと
これらは、作業療法を受けてぼんちょを理解する手助けになったと感じています。
2歳からスタートした児童発達支援(療育)
2歳から児童発達支援(療育)にも週1回通えることになりました。
ぼんちょが住んでいる地域では当時、療育は3歳から受け入れている事業所が多かったです。
ですが、2歳台で受け入れてくれるところが見つかりました。
早期に療育につながり、個別療育を通してぼんちょができること・できそうなことを丁寧に探してもらいました。
療育を受けることで生活の中で何に取り組んでいけば良いか示してもらえたことが助かりました。

実は療育に通うと決まった頃に保育園を退園して引っ越すことが決まったため、最初の児童発達支援事業所には4ヶ月しか通えませんでした。
短い間でしたが、とても寄り添っていただき私の心の支えになっていました。
MRI検査(2回目)を受けた
1歳で受けた初回のMRIから半年後の造影剤を使ってのMRIでした。造影剤を使うため、入院をして静脈注射で鎮静をしての検査となります。
2回目の検査で見るのは、1歳の時に見つかった病変に変化はあったかどうかです。
結果は、前回から特に変化はありませんでした。
今後もまだ変化を見ていく必要があるため、次回は「1年後」に再検査となりました。
担任の先生から保育園退園を勧められて退園と引っ越しを決意
重度知的障害とのちに診断される「ぼんちょ」が2歳になって医療や福祉の支援を受け始めた頃、保育園から退園を勧められました。
保育園退園についてどんな風に伝えられた?
ある日ぼんちょを迎えに行くと、

パトまめさん。今から少しお話良いですか。
別室に案内されました。

結論からお伝えすると、ぼんちょ君が3歳になったら保育園でお預かりするのは難しそうです。
3歳になると今より集団での活動が増えますし担任の数も減るのでぼんちょ君のためにもならないと思います。
こんな風に保育園の先生から退園を勧められました。
2歳児の頃、保育園退園を勧められてどのように受け止めたか
まず、泣いてしまいました。
自分なりにではありますが一生懸命仕事をしていました。子どもたちを育てていました。
そんな自分自身のいっぱいいっぱいだった気持ちがついにあふれてしまいました。
ショックではあったけれど、自分自身が精神的にも限界が近いことを感じていました。
また、
- ぼんちょの発達と周りの子との差がどんどん開いていること
- 保育園での集団生活が難しくなってきていること
も理解していました。2歳はそんな時期でした。
働きながら祖父母にも協力してもらって作業療法や療育にぼんちょを連れて行っていました。
ぼんちょ兄もまだまだ4歳で放っておくわけにはいきません。スケジュール的にもかなり余裕はありませんでした。
たくさん泣いた後に、たくさん考えました。色々考えた結果。もう仕事をやめようと決めました。
そして、
- 夫とパトまめが住み慣れている
- 協力的な実家がある
そんな地元へ引っ越そうと決めました。
重度知的障害児の母親の退職と家族の引っ越し
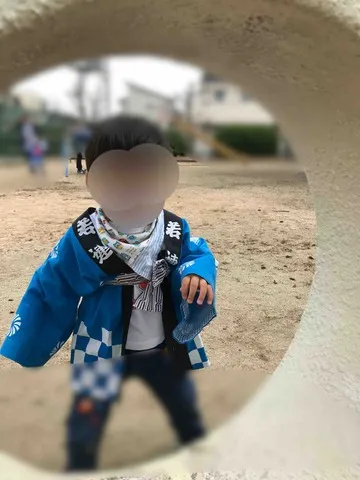
重度知的障害児「ぼんちょ」の母親の退職と家族の引越し・・・それを決めてからは早かったです。
まず、お世話になり始めたばかりの療育の先生に
- 保育園を退園すること
- 引っ越すこと
を伝えました。すると、
「せっかく保育園に通えているのだから、絶対に集団生活をした方が良いと思う。保育園や幼稚園に行かない場合、毎日療育に通う利用の仕方があるから引っ越し先の事業所を探したほうがいい」
と、アドバイスをいただきました。
そのアドバイスを頼りにGoogle検索をしたところ、引っ越し先の地域に良さそうな「児童発達支援センター」があることがわかりました。すぐに連絡をして見学をしました。とても良いところだったため利用希望を伝えたところ、次年度からの契約が決まりました。
児童発達支援センターに通い始めた頃のぼんちょの様子はこちらからどうぞ↓

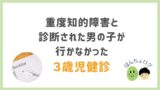
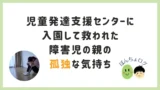
まとめ
重度知的障害児「ぼんちょ」の2歳児の頃の特徴や成長の記録をブログにまとめました。
2歳になったぼんちょの最初の半年間は、こんな時期でした。
- ぼんちょからの要求や否定のアクションが増えた
- 発達の遅れへの支援を受け始めた
- 集団生活が難しくなった
本人なりの「好み」や「嫌」という気持ちが身体を張った問題行動として現れ、育てにくさを感じることもありました。それでも家族以外の支援者・協力者にぼんちょを見てもらうことで、家族では気づけなかった子どもの特徴や傾向に気づけました。
それは、家族にとっても子ども本人にとってもプラスなことでした。
ですが、周りの同年齢の子供達との発達の差がどんどん開いていくことは止められず、保育園での集団生活が難しくなっていきました。
2歳で保育園退園を勧められてショックも受けました。引っ越しを決意してすぐに引っ越し先での児童発達支援センターの利用が決まったことは、本当にラッキーだったと思います。
発達の遅れがあったり障害が判明した時には
- 医療や福祉とつながることで付き添いや送迎が必要になる
- 過ごす環境を変える必要が出てくる
など本人はもちろん家族の生活もガラリと変化する可能性があります。そんな時に
- 頼れる人がまわりにいるか
- 頼れるサービスがあるか
も生活する上で大切になってきます。
もし同じような境遇の人がいましたら何か参考になることがあれば幸いです。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!