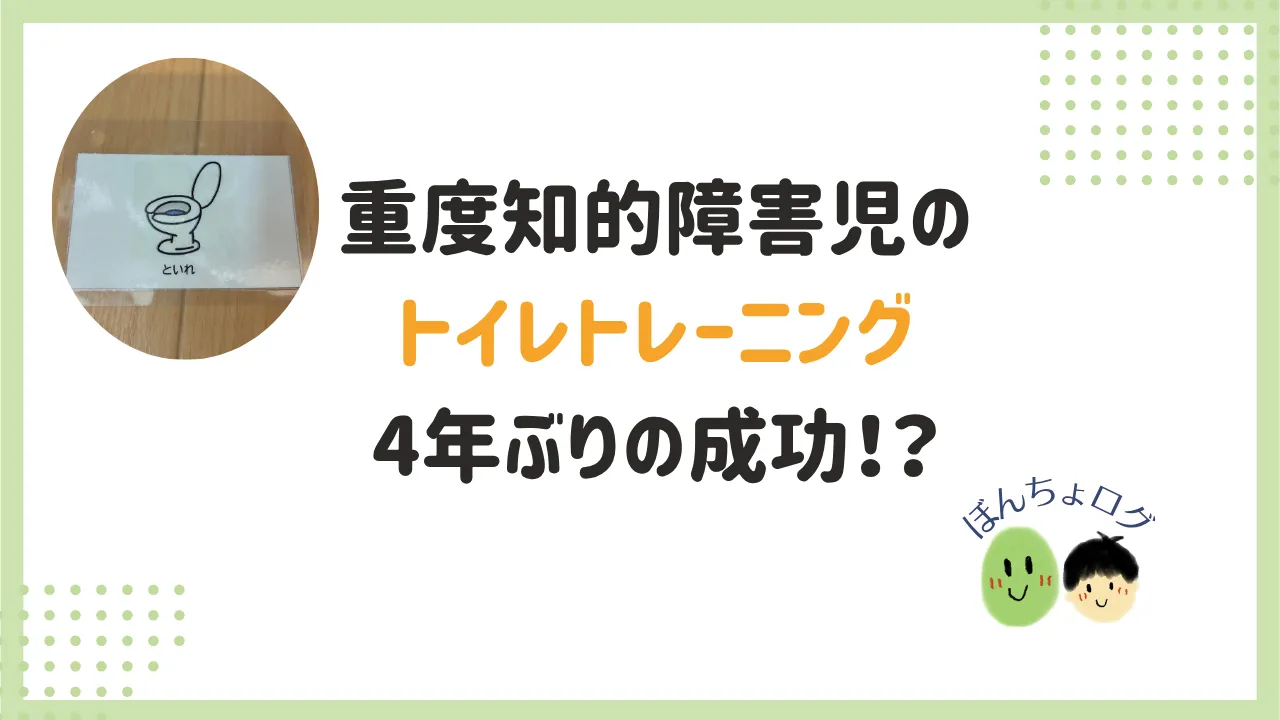重度知的障害児のトイレトレーニング方法を紹介します。
このブログでは、重度知的障害児のトイレトレーニング方法について紹介します。
ですが、1つ最初にお断りしておくと、我が家のぼんちょのトイトレ・・・
現在進行形です!
でも、だからこそ。
「なかなかオムツが外れない」というお仲間の皆様にとって参考になる可能性を信じて書いていきます。
それではいきましょう〜!
重度知的障害児のトイレトレーニングは何から取り組む?
重度知的障害児のオムツ交換はトイレで行う!その理由は?
重度知的障害児にトイレトレーニングをする場合に、まず取り組んだこと。それは、
オムツ交換はトイレでする
ということです。なぜ、オムツ交換はトイレでするのかというと
多くの人は排泄にまつわることをトイレでするからです
もちろん、身体の障害があるなどの理由から排泄にまつわることをトイレで行うことが難しい人もいます。その場合も、「多くの人に見られない場所で」「異性に見られない場所で」など、その人に合わせた環境下で排泄にまつわることを実施できるようにしていく必要があると考えます。
知的障害や自閉症の子どもに排泄に関するスキルをどう教えるのか。
知的障害や自閉症の子どもにスキルを教える方法の1つに、場所と活動を結びつける「構造化」という方法があります。
重度知的障害児ぼんちょのトイトレの第一歩は、オムツ交換をトイレですることで、「排泄」と「トイレ」を結びつけることでした。
立つことが難しい赤ちゃんの頃は、リビングなどでオムツ交換をする人が多いです。
また、幼児期になってもオムツが外れないうちは、家の中であればどこででもオムツを変えることが物理的には可能です。
ですが、立つことができるお子さんは、早めにオムツ交換をトイレでする習慣をつけておくと、
- 排泄のことはトイレで行う
- 下半身を露出する着替えは個室で行う
という行動を促すことに将来的に結びつきます。
重度知的障害児がトイレに入るのを拒否!どうする?
重度知的障害児とトイトレを始めようとした時に、幼児期にリビングなどでオムツ替えをすることが当たり前になっていて、いざトイレに連れて行こうにもトイレに入るのを拒否することが起こり得ます。
重度知的障害児ぼんちょもそうでした。その時の対応策を紹介します。
- リビングの出口などトイレに一番近い場所でオムツ替えをし、どんどんトイレに近づけていく
- トイレに移動する時のアイテムを決める
- ごほうびを用意する
いろいろ試してきました。それでも今でもトイレに入るのを嫌がる時はあります。
そういった時には、自宅だったら「せめてトイレのドアの前までは行こう」と促したり、好きなおやつを見せて励ましたり試行錯誤です。
どんな時も、合言葉として「排泄のことをトイレでするのは人間の常識!」を頭に置いて支援しています。
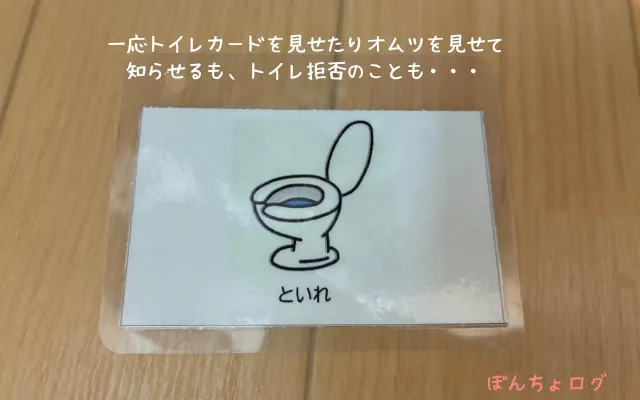
重度知的障害児のトイレトレーニングが成功しない時にどうする?
重度知的障害児のトイトレは子どもの状態を観察するのが大事
重度知的障害児のトイレトレーニングでは、次のような項目について子どもの現状を知ることが大事です。
| 機能的なこと | 貯められるのか、出そうとして出せるのか |
| 感覚的なこと | 出た(出した)ことがわかるか、不快がわかるか |
重度知的障害児とトイレトレーニングをしようにも、排泄というゴールに辿り着くまでのどの段階に我が子がいるかを理解するのってすごく難しいんですよね。重度知的障害と診断されたぼんちょも、
- 本人から排泄したサインが無いため、いつ出たかがわかりにくい
- 感覚が鈍麻
こういった理由から、普通に生活しながら観察していただけではよくわからない・・・という状態でした。
なので、私がぼんちょの排泄の状態を理解するのにとった対応策は・・・
家の中で下半身丸出し or 布パンツで過ごさせる
という方法でした。
前の章で、「多くの人は排泄にまつわることをトイレでする」と言っておきながら、すごい変わりようですが・・・
これは、子どもの状態を知るための方法だから致し方ありません。
実際に観察してみてわかったのは、ぼんちょの場合
- 濡れたのは分かっても本人は平気(不快じゃない)
- 自分の意思で出すことはできる(下腹部に注目して力を入れる様子あり)
ということでした。

一時期、自分の要求が通らなかったときに、なんとかして要求を通そうと、わざとオムツをずらして排泄して服を濡らすという問題行動が増えた時期がありました。こんなことができるなんて、自分の意思で出すことができる証拠ですよね。
重度知的障害児のトイトレ作戦を考えよう
重度知的障害児のトイレトレーニングの作戦を考えるには、前の章で知った子どもの状態を役立てます。
我が家の場合は、次のように判断しました。
- 布パンツが濡れて不快だから変えよう作戦→効果が薄そう
- たくさん飲水を促してトイレに誘う作戦→効果◯
- 下腹部に注目している時にトイレに誘う作戦→効果◯
このように、子どもの現状から考えて、効果がありそうな作戦を中心に取り組むことにしました。
重度知的障害児、4年ぶりにトイレで排泄!?
ある日の夜、寝る前にぼんちょの目線が下腹部にあることに気づき、トイレに誘いました。
そしてスムーズにトイレに座ると下腹部に力を入れて排泄に成功!
自宅トイレで成功するのは4年ぶりの出来事でした。
その後、連続で成功・・・とはいかなかったのですが、ゼロと1は違います。
これからも本人の状態を確認しながら作戦を立てて、諦めずに取り組もうと思った瞬間でした。
その次はさらに2ヶ月後に学校で成功!
まとめ
重度知的障害児のトイレトレーニングについて、実際に取り組んでいる方法について紹介しました。
トイレで排泄するのは、生きていく上で必要なスキルです。「できれば、いつかできてほしい」と願う親は多いはず。私もその1人です。
でもそれは、とても根気のいる長い戦いでもあります。
長い目で見て、親がしんどくなりすぎないようにやっていきましょうね。そのためにも闇雲に取り組むよりは、まずは排泄とトイレという場所を結びつけることと、子どもの状態を知ることが、効果的な作戦を立てるための近道だと言えます。
子どもの状態を知るためには園や学校、利用しているサービスとも連携してみんなで取り組んでいきましょう。
我が家の重度知的障害児ぼんちょのトイトレも、まだ現在進行中。
この記事を読んでくださった皆さまと共に、無理しすぎずにやっていきます!
今後も変化が現れましたら、こちらのブログで紹介しますね。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!