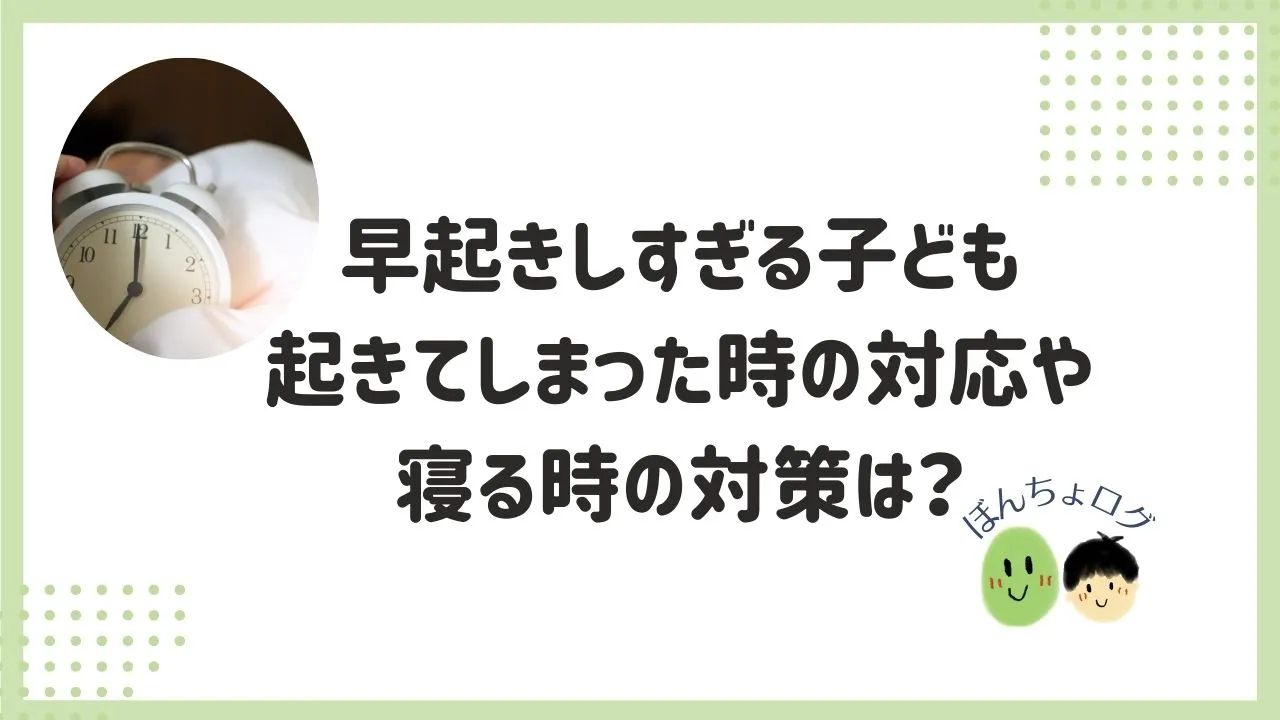ぼんちょは4時や5時に起きることがあります。
- 早朝に目覚めてしまう子どもへの対応に困っている方
- 睡眠環境を整えたいと思っている家庭
- 子育て中の親が日々の生活で活用できる具体的なアイデアや方法を知りたい方
この記事は重度知的障害と診断されたぼんちょの母親パトまめが過去の経験をもとに作成しています。
早寝・早起きは良いことだけど、「いくらなんでも早起きすぎる!」という時間に起きることがある重度知的障害児のぼんちょ。
子どもが「早起きすぎ」と感じる瞬間、親としてどう対応すればいいのか迷ったことはありませんか?
特に、4時や5時といった早朝に起きられると、家族全員の生活リズムにも影響を及ぼします。
今回は子どもの早起きの理由やその対策、そして早起きしてしまったときの対応方法をぼんちょの実体験をもとに紹介します。
夜間のオムツの選び方から環境調整まで、実用的なヒントが満載です。同じように「早起きすぎる」子どもに悩むご家庭に参考になることがあれば幸いです。
早く起きてしまった時の対応は?

オムツや排泄の確認
子どもが早起きする時に考えられる理由に排泄に関することがあります。
- 排泄をしたくて起きた
- 排泄をしてしまってオムツや下着が濡れて気持ち悪くて起きた
排泄ができたりオムツや下着を替えてスッキリすると再度寝始めることがあります。
電気やテレビを付けない

ぼんちょが4時や5時に起きてしまった時に決めていることがあります。それは、
決して部屋の電気を付けない。
テレビも、もちろん付けない。
これを徹底することに決めています。
たとえ早く起きたとしても、みんなはまだ寝ている時間。
それをぼんちょに伝え、理解を促しています。
安全を確保して自分は休む
まだまだ見守りが必要な子どもが早起きをした場合に、親は一緒に起きます。
ぼんちょは1人で放っておくことはできないため私も一緒に起きています。
ですが、遊び相手はしていません。
とはいえ、ぼんちょも何もないと走り回るなどかえって望ましくない行動をしかねません。
そこで、チラシを破くなど安全で静かにできる作業を「これなら今やってもいいよ(本当はまだ寝てる時間だからな)」と促しています。
私も一緒にリビングの暗い部屋で過ごしますが、相手はせずに目をつぶって横になって休みます。
「まだみんなは寝ている時間」ということを伝えるためでもあります。
早起きすぎなのを防ぐ!寝る前の対策
そもそも早起きの原因は?
ぼんちょの場合は、早起きの原因を考えた時に次のことが思い当たりました。
- 尿量が増えてオムツが受け止めきれない
- 早い時間に寝てしまう
- 温度が不快で起きてしまう
- 日光の問題
もちろん早起きの原因がこれらのどれにも当てはまらずよく分からないこともあります。
その場合は、もう仕方がないので早起きしてしまった時の対応で「みんなはまだ寝ている時間」ということを伝えて静かに過ごすことを学習する機会にします。
ですが、示したような原因が思い当たるときは、対策できるかもしれません。
尿量が増えてオムツが受け止めきれない
ぼんちょはまだオムツで寝ています。
オムツには体重で「◯kgまで」とサイズの基準が示されていますが、夜に関してはこれがあまり当てになりません。
もしも、日中は大丈夫でも夜間に漏れることが多い場合は夜間用に適したオムツを用意することをおすすめします。
ぼんちょは日中は「メリーズパンツのビッグより大きい」
夜間は「ムーニー オヤスミマン スーパービッグサイズ男の子用」を使用しています。
体重24kg時点ではちょうど良く、ほとんど漏れることはありません。
他にもパンパースの夜用も試しましたが漏れました。
寝る前に飲水量でも夜間や朝方の排泄量が変わってくるため、もしも夜だけ漏れて睡眠の妨げになっている場合は夜用オムツを試すことをおすすめします。
早い時間に寝てしまう
早い時間に寝てしまったら
そりゃ早く起きるわ。
ぼんちょが18時台に寝てしまった時は夫も私も震えてます。「明日何時に起きるんだろう?」って。
でも、疲れていてどうしてもその時間に寝てしまうこともあるんですよね。
だからそういう時は大人もなるべく早めに寝てしまうことにします。
また、疲れて夜早く寝そうだなと思った時にはあえて「昼寝」を促すのも効果的です。
16時や17時に昼寝すると夜が寝られなくなるという子は控えるべきです。
ですが、ぼんちょの場合は案外10分〜15分程度の昼寝はあまり夜の睡眠に影響しません。
むしろ短い昼寝を夕方にしたほうが夜もスムーズに寝られることがあるくらいなので、疲れてそうだなという時は昼寝できる環境を整えて昼寝を促しています。

夕方に昼寝する時は絶対に20分以下で起こすようにしています。寝すぎると夜に寝られなくなるからです。
温度が不快で起きてしまう
これは暑くても寒くてもダメですね。
夏はエアコンをタイマーにして寝ると、切れた後に朝方起きることがありました。
昔に比べて夜も暑いことが多いです。
子どもが暑さで起きることが続くようならエアコンを付けっぱなしにすることをおすすめします。
また冬は冬で、窓に近いところで寝ている場合は特に冷気を感じて起きることがあります。
なので、窓から離れた位置で寝るか、窓からの冷気を遮断する工夫をおすすめします。
日光の問題
ぼんちょは冬は比較的6時以降に起き、春から夏にかけて早起きになる傾向があります。
これは日が登るのが春・夏のほうが早いからです。
カーテンは遮光カーテンかつしっかり閉めてから寝ることをおすすめします。
まとめ
子どもの起床が「早起きすぎる」問題は、オムツの不快感や部屋の環境、睡眠リズムなどが原因になっていることがあります。
まずは原因を探り、適切なオムツの選択や睡眠環境の改善を行うことをおすすめします。
また、早起きの原因が分からないこともあります。そんな場合は早起きをした時にどうするか、対応を決めておくことが大切です。
早起きしてしまった際には、部屋を暗く保ち静かに過ごすことでまだ他の人が寝ていて静かにすべきことを伝えることが可能です。
同じように「早起きすぎる」お子さんがいらっしゃるご家庭にとって参考になることがあれば幸いです。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!