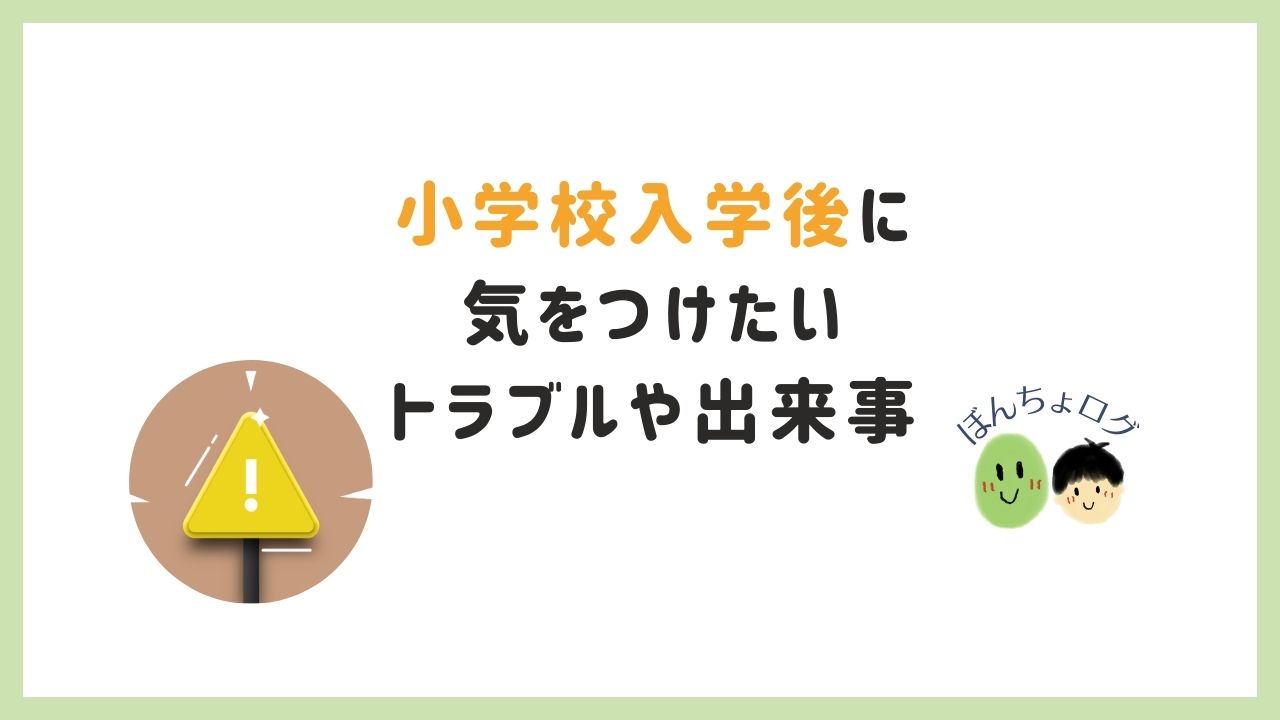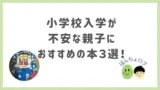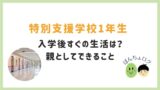今回は実際に小学校入学直後に周囲で起こったことを紹介しながら、保護者として気をつけるべきことを紹介します。
重度知的障害「ぼんちょ」の兄である「ぼんちょ兄」の小学校入学後の経験をもとに親として気をつけたいことをまとめます。
小学校入学直後の不安な時期に保護者が直面しやすい「うわさ話」や「突然知らない子が家に訪ねてくる」といった実際の体験をもとに、気をつけたいポイントを紹介します。
支援学校入学後に気をつけたいことはこちら↓
小学校入学後に聞くうわさ話に気をつけよう
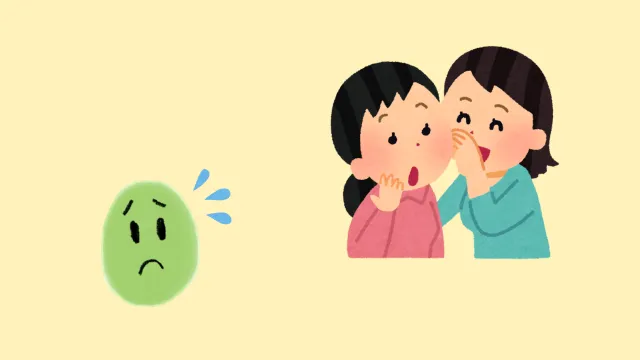
先生や子どもたちについてのうわさ話を耳にする
小学校入学後ってどの保護者も「情報」がほしくなるんですよね。
保育園や幼稚園から小学校に入学すると保護者は次のことを実感します。
- 学校に行く機会が少ない
- どんな先生・子どもがいるか把握しづらい
- 新しく一緒になる保護者と関係ができにくい
すると不安になります。
「我が子の先生は良い先生なんだろうか?」
「我が子のクラスは落ち着いているだろうか?」
「暴力を振るう子が周りにいないだろうか?」
不安になった保護者はどんな行動をとるかというと、
- 知り合いの保護者に学校のことを尋ねる
- 話を聞き出したいがために自分の知っていることを他の保護者に話す
このようにして「うわさ」がどんどん広がっていくんですね。
特に注意してほしい!良くない保護者同士のうわさ話
入学後に聞くマイナスな情報には2種類存在しました。
- 自分の子どもが当事者
- 自分の子どもは部外者
特に注意したほうがよいのは「自分の子どもは部外者」である情報です。
このうち、「自分の子どもが当事者」である情報とは、自分の子が関わっている話です。
例えば、
「担任の先生のひらがなの直しが厳しすぎる気がするんだけど、そちらのクラスはどう!?」と他のクラスの保護者に尋ねること
「学校の帰り道に同じ班の子が公園で遊ぼうと誘ってきて困ってるみたいなんだけど、家で何か聞かない?」と同じ下校班の保護者に尋ねること
こんな話が「自分の子どもが当事者」である情報にあたります。
我が子に起きていることが心配だったり事実を確認したくて他の保護者に相談するようなケースです。
これは、ありますよね。
いわゆる相談だったり愚痴だったりを仲良しの保護者に話すことは全くないとは言い切れません。
では、「自分の子どもは部外者」である情報はどうですか?
例えば、
「入学式で立ち歩いていた子、幼稚園の頃から多動気味だったけど療育も行ってなかったらしい。同じ幼稚園だったお母さんが言ってた。」と話すこと
「3組には暴れん坊3人衆って呼ばれる子たちがいるらしいんだけど、どの子かわかる?3組の真面目な女の子のお母さんが言ってたから間違いないと思うんだけど」と3組の保護者に尋ねること
「隣のクラスの先生って1年生の担任なのにすっごく怒鳴るらしいよ。当たらなくて良かったね。」と話すこと
こんな話は「自分の子どもは部外者」である情報ですよね。ちなみに実際にすべて他の保護者から聞いた話です(少しズラしてフェイクを入れていますが、ほぼ同様)。
どの話も、話し手のお子さんはそこに登場しないんですよね。
何か被害を受けたとかでもなく
めちゃくちゃ部外者。
それでもこんな「うわさ話」が入学後はめちゃくちゃ増えます。
それは、みんな不安・心配だからです。気持ちはわかります。
でも、冷静に考えると気持ちの良いことではないですよね。
逆に我が子が知らない保護者たちの間で話題になってたら嫌じゃないですか。
だから、入学後に何でもかんでも知った情報を言ってくる保護者には要注意ですし、
自分自身も人に話す時には「話す内容」と「話す相手」にはよく気をつけましょう。
うわさ話に踊らされないために
他の保護者から知った学校生活のマイナス情報が自分の子どもに関係することだった場合は、まずは自分の子どもに確認です。ただし、まだ1年生なので起きたことを正確に伝えることが難しいお子さんもいます。
なので事実確認や解決が必要なことである場合は、自分で足を運んで確認するか学校の先生に確認や解決をお願いしましょう。
他の保護者から知った学校生活のマイナス情報が自分に子どもにとりあえず直接関係しないことだった場合は、
「知らんがな!」
で終了です。
でも、情報を聞いてしまったことで心配な気持ちが生まれる人もいますよね。
例えば学校の先生の悪評判とか。
ですが、ほとんどの情報は知ったところで我が子が被害を受けなければ関係ない情報です。
しかも、その情報が本当かどうかもわからなければ、我が子にとっては直面しても問題にならない可能性だってあります。
ろくに関わってもいない先生や友達に対して「うわさ話」を聞いてマイナスイメージを持つことは、自分の子どもにとっても悪影響を与えかねません。
入学後の不安になりやすい時期は特に、親として他人の「うわさ話」に振り回されないようにしましょう。
突然知らない子どもが家にやってきたら?

こんな場合は要注意!
地域の子どもの人数が少ない小学校の場合は入学前から全員知ってる場合もありますが、多くの場合は入学と同時に新しく出会う友達がいるはずです。
入学後は、新しい友達と遊びたいという気持ちが生まれるお子さんも多い時期です。
実際、入学後の1ヶ月の間に初めて我が家を訪ねてきた子は5人以上いました。
遊ぼうと誘われた時にぼんちょ兄もすごく嬉しそうで、親としても喜びを感じました。
ですが、こんな場合は要注意
- ランドセルのまま家に来る
- 家に入ろうとする
実際にありました。
ランドセルで来る=家に帰っていない
ということです。あまりにも続くので担任の先生にお手紙を書いて相手の保護者に状況を伝えてもらったことがあります。
また、突然来て家に入ろうとする子に対しては、
「まだ、あなたのお母さんとお父さんを知らないから。勝手に家に入れるのは良くないから外で遊んでおいで」
と言って外で遊ぶよう促しました。
「要注意」と書きましたが、迷惑だからとかではなく同じ地域に住む子を1人の大人として見守る気持ちで対応していました。
特に相手のお子さんや親御さんについてよくわからないうちは、
- ルール的に良くないことが起きている時は学校経由で親御さんに状況を知らせる
- 家に入れるのは相手の親御さんに確認してから
という対応をしていました。
入学後に知らない子どもの保護者と連絡をとる方法
知らない子どもが家にやって来るようになると相手の保護者の連絡先が知りたいケースが出てきます。
例えば、本当に仲良くなって我が子が家で友達と遊びたがっている場合などです。
参観日など学校行事で会う機会があれば、そこで連絡先の交換が可能です。
ですが、それよりも前に知りたい場合にはお子さんに私の「LINE ID」「電話番号」を書いたメモを持たせました。
個人情報を持たせることが心配な場合は、お子さんと一緒に家に行かせてもらって直接渡したりポストに入れさせてもらうのも方法の1つです。
入学後に子ども1人での外出をどこまでOKにするか
入学後には友達から外で遊ぼうと誘われる機会が増えます。
我が子ひとりで外出させるかどうか悩みませんか?
私は悩みました。幼稚園までは必ず大人がついて行っていてので。
私の場合は、まだよく知らない子と遊ぶ時には自分もついて行っていました。
ですが、我が家には重度知的障害のぼんちょがいることもあり、しばらく様子を見て大丈夫そうだったらぼんちょ兄を残して先に帰りました。
場所を把握したかったので、ぼんちょ兄にはGPSを持たせました。
実際に使用していたのはこちら。学校にも持たせていました。↓
ただし当時は「まもサーチ2」だったのでバージョンアップしていますね。
小学2年生になってからは時計や通話機能もついてるこちらに変更にしています。学校には持って行っていません。↓

完全に1人で遊びに行かせるようになったのは、登下校に慣れてきた1年生の夏休み前くらいです。
具体的に、「学校か家から学校までの間の公園だったら1人で行ってもOK」というルールを決めました。
1人で遊びに行くようになってからもGPSは持たせることを徹底しています。
まとめ
小学校入学直後は、子どもの新しい環境に慣れさせるだけでなく、保護者自身も戸惑いや不安を感じる時期。
そんな中で「うわさ話」に振り回されてしまうと、必要以上に心配になったり誤った判断をしてしまうこともあります。
他の保護者から聞いた話が本当かどうかはわかりませんし、それが自分の子どもに関係あるかどうかも重要なポイント。
もし不安を感じるなら、まずは子どもや学校に直接確認することが安心につながります。
また、突然訪ねてくるお友達への対応や、1人で外出させるタイミングについても、各家庭でルールを決めておくことでトラブルを防ぐことができます。事前に方針を決めておくと、いざという時にも落ち着いて対応できますよ。
「うわさ」に流されず、我が子の様子と家庭の方針を大切に。
焦らず、親子で少しずつ小学校生活に慣れていけますように。
このブログが小学校入学後のお子さんがいるご家庭に参考になることがあれば幸いです。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!