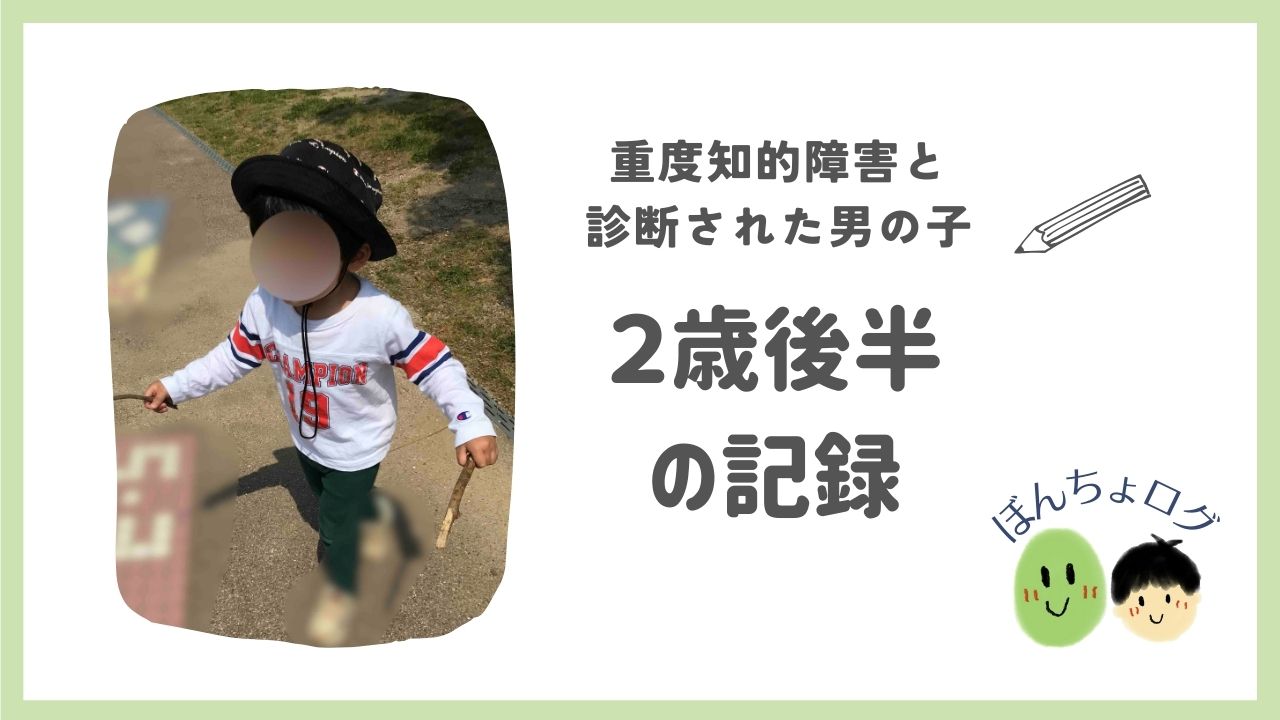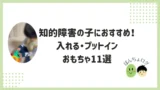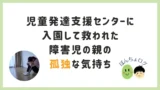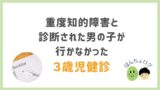重度知的障害と診断された「ぼんちょ」の2歳半から3歳までの様子をブログで紹介します!

2歳半では保育園を退園して引っ越したんだよね!

引っ越し先では児童発達支援センターに通うことが決まりました。

重度知的障害児「ぼんちょ」の2歳児後半時期(3歳前)の特徴や成長の記録をブログにまとめます。
ここに書いてある3歳前の成長記録がすべての知的障害の子どもに当てはまるわけではありません。
ひとりの重度知的障害の男の子の過去の記録として誰かの参考になれば幸いです。
2歳後半の特徴の前に!2歳半までのおさらい〜ぼんちょの発達への支援スタートと保育園を退園

2歳前半に発達の遅れへの支援や保育園退園など生活がガラリと一変しました。
重度知的障害と診断された子の2歳7ヶ月から3歳までの発達は?|療育で立てた目標に向かって頑張る日々
重度知的障害と診断された「ぼんちょ」の2歳台後半の発達の記録をブログにまとめていきます。
2歳台の後半は、毎日療育を受け始めたことによって少しずつ成長が見られた時期でした。
そんな当時のぼんちょの成長記録をまとめます。
なかなかできることが増えない知的障害児に試したことがすぐ知りたい人はこちらからジャンプ
児童発達支援センターへの通所開始!身辺自立(食事・排泄・着脱)には明確な目標が決められた
重度知的障害児ぼんちょは2歳7ヶ月の時に児童発達支援センターに通い始めました。
通い始めて良かったことは、ぼんちょの今の状態を評価した上で文字化して目標設定してもらえたことです。

身辺自立が年齢に対して「全然できていない」ってことはわかるけど、療育に通うまでは「何ができそうか」「何を頑張っていいか」がわからなかったんですよね
「食事」「排泄」「着脱」それぞれの最初の目標が定まりました。
| 項目 | 目標 | 結果 |
| 食事 | 大人と一緒にフォークを持って1口食べることができる | 3歳までに目標達成 |
| 排泄 | 誘導で定時にトイレへ行き便座に座ることができる | 3歳までに目標達成 少ない回数ではあるがタイミングが合った時にトイレでの排尿に成功 |
| 着脱 | 大人と一緒に半袖を着ることができる(手を動かして協力する) | 手を動かして協力することが増えたが、本人のコンディション(昼寝後や気が散る状況)によっては大人が腕を持って袖を通してあげないと難しい |
目標がはっきりしたことで家庭でも「これを頑張ったらいいんだ!」とわかって気持ちが楽になりました。それまでは
「やってあげる」
「サポートする」
ばかりで、本人が頑張る部分を設定することができていなかったんですよね。これに気づけたことは、ぼんちょの成長というより
母親パトまめの成長!
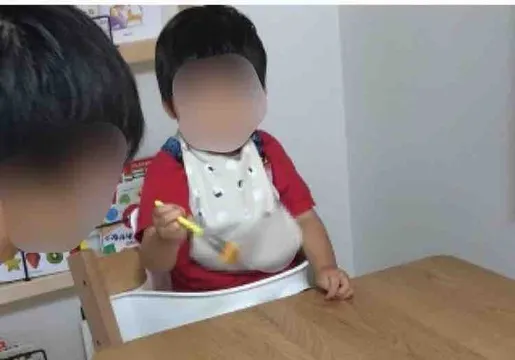
コミュニケーションでは「実物」を見て次の予定を理解できるようになった
療育では、「実物を見て、次の活動場所に大人と一緒に移動することができる」という目標が立てられていました。具体的には、次の順序で取り組むことによって実物を見て移動できるようになりました。
- 使用する皿を見せて食事・おやつに誘う
- 活動を終えて食事場所に移動する
もともと「ごはん」などの短い単語で移動できていたのを視覚情報でも理解して動く練習を積み重ねていきました。これは発語のないぼんちょが将来、絵カードコミュニケーションすることも見据えてのことです。
重度知的障害児ぼんちょの遊び方はマイルールやこだわりが強め
重度知的障害児ぼんちょは2歳の前半から引き続き、遊びではマイルールやこだわりの強さが目立ちました。
外で遊ぶのは遊具よりも自然が大好き
重度知的障害児ぼんちょの外遊び。外では遊具で遊べるようになってほしいと願っていたのですが、最初は嫌がって大泣き。

草・木・砂・葉っぱが大好きなんだもん
児童発達支援センターには園庭があり遊具がありました。気持ちがのっている時に繰り返し誘ってもらうと次第に複合遊具に近づくことができ、滑り台に大人と一緒に登ることができるようになっています。
ルールの理解が難しく、簡単な操作で変化がわかりやすいものを好む
重度知的障害児ぼんちょが児童発達支援センターに入園した当初、室内で集中して1人で遊べるおもちゃがとても少なかったです。この時期に比較的1人でも集中できたのは、次のような遊びです。
- おもちゃ・物を出し入れする
- 磁石やマジックテープをくっつける・はがす
- 重ねたり・バラバラにする(分解する)
これらの操作が入る個別課題やおもちゃには、比較的興味を示しました。
療育ではプットイン課題(ペグを筒に入れる)を取り入れた個別活動をしてもらっていました。
ですが1個入れたら容器から取り出そうとするなど、「全部入れたら終わり」という課題の意図を理解して最後まで取り組むことは、まだ難しい様子がありました。
重度知的障害児ぼんちょの「できること」・「興味」を増やすためにまずしたこと
重度知的障害児ぼんちょの「できること」「興味」を増やすために「大人がぼんちょの動作の逆模倣をする」ことに取り組みました。
具体的には室内で一緒に遊んでいるときに、ぼんちょがおもちゃで遊ぶ横で同じおもちゃを使って大人が動作を真似ていました(動作の逆模倣)。
「できることや興味を増やしたい」と児童発達センターの先生に相談すると、
できることや興味を増やす前段階として、他の人の行動に目を向けてもらう必要があるかもしれない。まずは、ぼんちょ君が興味があるものを2つ用意して、ぼんちょ君の動作を大人が逆模倣してみましょう。
とのアドバイスをもらいました。実際に取り組んでみると、次第に他者(大人)がやっていることに注目する時間が増えていきました。
ぼんちょが注目できた時には次の方法も試しました。
- 同じおもちゃを使って少し違う動作を加える
- 興味を持って遊んでいるおもちゃに似た別のおもちゃを持ってきて使うところを見せる
すると、少しずつ遊び方が変わってきたり興味の持てるものが増えたりしました。

他の人がしていることに注目できるようになることがぼんちょの世界を少し広げてくれました。
県内での引越しに伴う環境の変化〜重度知的障害児ぼんちょ2歳後半の出来事の記録
重度知的障害児ぼんちょと家族は県内の別の市に引っ越しをしました。
この時点でぼんちょが利用していた障害福祉サービスは療育(児童発達支援)のみ。
転入先の自治体で療育のための「通所受給者証」を発行してもらう必要がありました。
引っ越しの時に必要な療育に関する手続き
子どもが療育などの障害福祉サービスを利用していて引っ越すときに必要なことは次のことがあります。
重度知的障害児ぼんちょの今回の引っ越しの時の状態は次のとおりです。
- 療育手帳は取得なし
- 日中一時支援等の地域生活支援事業の利用なし
- 県内の他の市への引っ越し
この状況ですべきことは療育のための受給者証の申請です。
この経験から先に大事なことをお伝えします。
引っ越しの際に療育の受給者証の手続きをする時は・・・
必ず転入先の自治体の担当課に手続き方法を問い合わせましょう!
実はパトまめは転出前の自治体に問い合わせをして、間違った手続き方法を提示されて失敗しました。
どんな失敗だったかは、こちらの記事でお話してるのでよかったらどうぞ。
引越し後、新しい住居にはすぐ慣れることができました

重度知的障害児ぼんちょにとって、住む場所が変わるのはとても大きな変化なので心配していました。
ところが、思った以上にぼんちょもぼんちょ兄も新しい家をすぐに受け入れることができていました。
引っ越し前に住んでいた家よりも間取りが増えて(2LDK→3LDK)広くなったため、兄弟同士での衝突が少なくなったのは嬉しい変化でした。
重度知的障害児ぼんちょは2歳7ヶ月で児童発達支援センターに入園
重度知的障害児ぼんちょは2歳7ヶ月の時に児童発達支援センターに入園しました。

忘れられない入園式でのぼんちょの様子とは?
入園式の日。入園式までの待ち時間に他の子どもたちはおもちゃに一目散。
そんな中ぼんちょだけは先生や保護者の周りをぐるぐる回ってじーっとひとりひとりの顔を見て回っていました。
慣れない場所での確認作業的な行動だったのか今でもよくわかりませんが、そんな行動をとっていたのは入園した子どもたちの中でぼんちょだけだったため印象に残っています。
2歳台で入園したのはぼんちょともう1人だけ。あとは3歳でした。
あとから
「3歳の子の方が優先されるから2歳で入園できたのはラッキーだよ」
と先輩ママから聞きました。
児童発達支援センターに入園後は行き渋りなし
保育園の時はある程度の期間「ならし保育」があったのですが、児童発達支援センターは入園式の翌日のたった1日の午前中だけ保護者同伴。それ以降はお任せする・・・という流れで療育生活が幕開けしました。
ぼんちょは行き渋りもなくすぐに慣れました!
おそらく保育園で集団生活に慣れていたのはプラスでした。
住まいも変わった
日中過ごす場所も変わった
初めは環境の変化を心配しましたが、良いスタートが切れました。
保護者にとっての児童発達支援センター:初めて他の保護者に障害のことを話せた
児童発達支援センターに入るまでにぼんちょの障害について他の保護者に話すことはありませんでした。
保育園に通っている間に話したことは一度もなく、退園する前日の迎えの時に出会った保護者に
「実は知的障害があって明日退園するんです」
と初めて伝えたくらい(めちゃくちゃ驚かれた・・・!)。
児童発達支援センター入園式の次の日の午前中、保護者が子どもに付き添う時間がありました。
他の保護者と話して思ったのは、

なんて気が楽なんだ・・・!
みんな自分の子に発達の心配ごとありきで入園しています。
「まだ言葉が出ていなくて・・・」
「こだわりが強くて・・・」
みたいな話で「わかるわかる」とうなずき合える空間。
その後も保護者会活動でおしゃべりしながら保護者同士の仲は深まっていきました。
まとめ
重度知的障害児「ぼんちょ」の2歳児後半時期(3歳前)の特徴や成長の記録をブログにまとめました。
重度知的障害児「ぼんちょ」の2歳半から3歳までの期間は次のような時期でした。
- 児童発達支援センターに通い始める
- 療育での目標が明確になってぼんちょへの支援方法が具体的になった
大きな環境の変化について最初は心配しましたが、ぼんちょが慣れるのは想像以上に早かったです。
児童発達支援センターに通い始めたことが家族にとってもぼんちょ本人にとっても転機となりました。
- 子どもに合った個別的な支援をしてもらってフィードバックしてもらうことで保護者にとっても学びが多い
- 発達の遅れや育児の困難さを感じている保護者と共有し合うことができる
など、家族ににとっても良かったことがあります。
もし同じような境遇の人がいましたら何か参考になることがあれば幸いです。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!