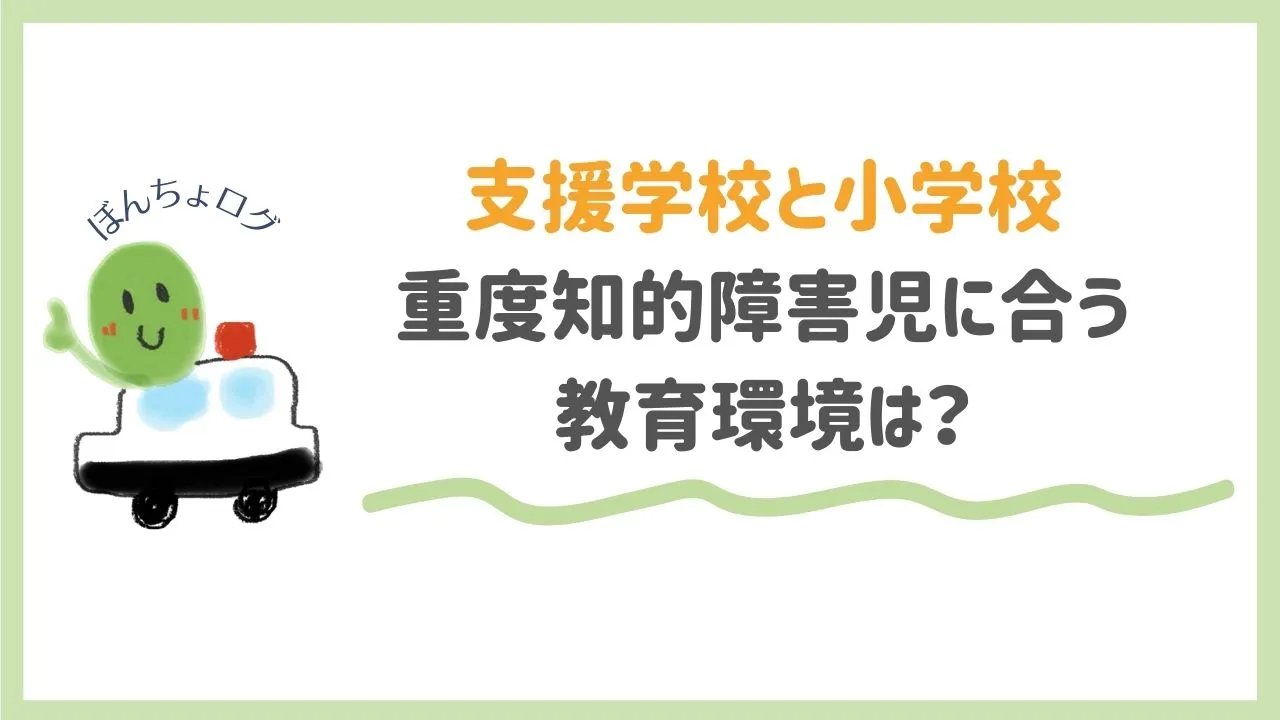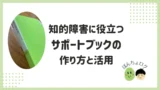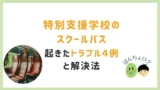重度知的障害「ぼんちょ」の就学。ぼんちょについては「特別支援学校に行くか」「小学校に行くか」あまり悩まず支援学校に決めました。でも周りに悩んでいたお母さんはたくさんいました。
重度知的障害の子の就学について、特別支援学校に就学するのと小学校に就学するのとでどんな違いがあるかやそれぞれのメリットについてブログにまとめます。
そもそも就学先はどうやって決まるのかや、就学先の選び方についても自身が経験したことや周りの家族お話を踏まえて説明します。
特に重度知的障害の中でも
特別支援学校に通うか
小学校の特別支援学級に通うか
迷われている親御さんにとって参考になることがあれば幸いです。
「重度知的障害」と同じ診断名がついていてもひとりひとりは違いますし、家庭の状況や家族の考え方、住んでいる場所でも選択肢や最終的にどうするかが変わってきます。
あくまで今回のブログ記事は1つの参考として読んでいただけますと幸いです。
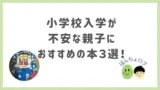
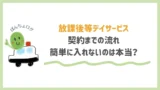
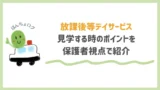
重度知的障害児の就学選択:特別支援学校と小学校特別支援学級の違いって?
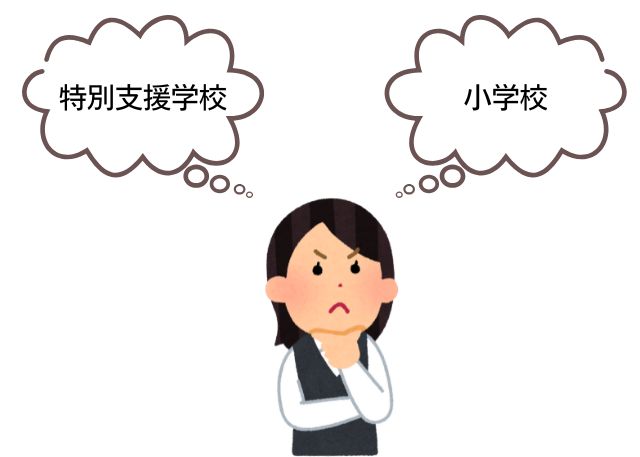
重度知的障害児が特別支援学校に就学するメリットとデメリット
重度知的障害児にとって特別支援学校は就学先の選択肢の1つです。
特別支援学校は、障害のある子どもが個々のニーズに応じた教育を受けられるように設計された学校です。
重度の知的障害や身体障害、発達障害を持つお子さんに特化したカリキュラムが提供されます。
- ひとりひとりに合った個別の指導計画で対応してくれ支援が充実している
- 1クラス(小学部では基本生徒6人)に対して先生が1人以上
- 特別支援の免許を持った教員が対応してくれる場合が多い
- 障害を持つ子ども同士の交流、保護者同士の交流が可能
- 医療ケアやリハビリの支援が受けられる学校もある
- 小学部から中学部まである
- 自宅から学校までの距離が遠く通学時間が長い場合がある
- 障害を持たない子や地域の子どもたちとの交流機会が少ない
- 小学校よりも机上学習は少ない
- 小学校と比べ、下校時間が微妙に早い
重度知的障害児が小学校の特別支援学級に就学するメリットとデメリット
重度知的障害児も小学校を就学先として選ぶことができます。
小学校の中でも特別支援学級は、小学校内に設置された知的障害を持つお子さんが入ることのできるクラスです。
知的障害を持つお子さんが入ることのできる知的特別支援学級と、知的障害を持たない発達障害を持つお子さんが対象となる情緒支援学級があります。また、他に特定の支援が必要なお子さんが対象となる支援学級(難聴特別支援学級など)がある場合もあります。
ここでは、知的障害のお子さんが入ることのできる特別支援学級のメリットとデメリットについて紹介します。
- 自宅から距離が近く通いやすい範囲にある
- 地域の子どもたち、障害を持たない子どもたちとの交流機会が多い
- 国語や算数では個々の進度に合わせて学習することができる
- 重度の障害に対する支援は、行く学校の方針や担任の先生によることが多い
- 保護者が学校生活に協力する頻度が多くなる可能性がある
- 特別支援学校に比べて、障害についての専門的な知識がない教員もいる
重度知的障害児は特別支援学校や特別支援学級に就学することを自由に選べるのか?

結論からお話すると、重度知的障害児は特別支援学校に行くか特別支援学級に行くかを完全に自由に選ぶことはできません。
特別支援学校に行くにしても
特別支援学級に行くにしても
お住まいの地域の教育委員会からの判定が必要です。
各自治体で決まっている期間に発達検査を受け、その結果を期限までに用意して申請する必要があります。
その申請をもとに、各自治体の就学支援委員会が保護者の意見を聞き取り、所属する園などに対象児の観察を行い、総合的に判断して決定されます。
その結果、「特別支援学級に適している」という判定をもらった場合は特別支援学校に行くことはできません。
「特別支援学校に適している」という判定をもらった場合は、最終的に特別支援学級を選択することもできます。
この判定基準はお住まいの自治体によって基準が異なるため、一概にこうだとは言えません。
実際にXなどでの就学判定結果のポストを辿っていくと、IQ50未満でないと支援学校の判定が出ないという自治体から軽度知的障害でも支援学校の判定が出る自治体まで、さまざまであることが見受けられます。
どの地域に住んでいても一番悩むのは、ギリギリ支援学校の判定が出るか、支援学級の判定が出るか微妙なラインにいる人です。
その場合は、判定が出される前に次の準備をします。
・かかっている医療機関で医師の意見書を用意してもらう
・所属している園からの意見書を用意してもらう
この準備をしておくと判定が出される前にその就学先を希望している理由や支援の必要性について就学支援委員会により具体的に伝わります。
なぜその就学先を希望しているのかを、保護者だけの意見としてではなく、子どもに関わるチームの意見として示せるように準備できると、より納得できる結果が得られやすいかもしれません。

パトまめの住む地域は、IQ50以上だと特別支援学校の判定が出ないと言われる地域です。このような地域ならではの情報は、児童発達支援センターで出会った先輩保護者から教えてもらいました。
重度知的障害を持つ子どもに合う教育環境の選び方
子どもの障害の程度と支援ニーズを把握する
「障害の程度」と「支援ニーズ」を把握するために次のことについて子どもの状態を整理します。
- 身辺自立がどの程度自立しているか
- コミュニケーションがどこまでとれるか
- 集団生活ができるかどうか
整理しておくポイントは次のとおりです。
| 項目 | ポイント |
| 身辺自立 | ・「食事」「排泄」「着脱」のそれぞれについてどこまでは自分でできて、どこからは手伝いが必要なのか |
| コミュニケーション | ・先生からの指示や友達からの声掛けをどの程度まで理解できるのか ・特定の方法を使えば理解できるのか |
| 集団生活 | ・その場にいられるか ・移動が必要な際にスムーズに移動できるか ・困った時に助けを求められるか |

なかなか我が子の「障害の程度」や「支援ニーズ」を家族だけで把握して整理するって難しいですよね。なので、お世話になっている病院や療育(児童発達支援)の先生などとも相談して確認することをおすすめします。
学校の設備や支援体制を確認する
子どもの障害の程度と支援ニーズを整理した後は、実際に通いたいと思う学校にそれを支援できる設備や支援体制があるかを確認しておく必要があります。
特に小学校の特別支援学級の場合は、学校ごとの環境や支援体制に差があります。
学校の規模やその時の教職員の考え方にも左右されます・・・。
入学前に子どもの障害の程度や支援ニーズを伝えて、それに対して「対応してもらえること」と「対応するのが難しいこと」を整理しておく必要があります。
その上で、学校だけでは対応が難しいことがあるとしたら、将来的に対応が可能そうか、保護者として協力できそうなことがあるかを考えます。

現状、重い障害がある場合は特にすべて学校にお任せというわけにはいかないことが多そうです・・・
障害が重い場合、より個別的な対応が必要になることが多いため、学校で対応してもらえることを教えてもらった上で、対応が難しいことについては、家庭で対応できるかどうかの検討も必要になります。
通学距離と通学手段を確認する
特別支援学校は、地域によっては遠方になることがあります。
まずは、現実的に通える範囲に支援学校があるかどうか、また、スクールバスの利用ができるかどうかの確認が必要です。
バスを利用する際は、どこからバスに乗ることができるのかやバスに乗る時間がどれくらいの長さになるかも確認しておきたいところです。
もしも現実的に毎日通える範囲に特別支援学校がない場合に、寄宿舎のある特別支援学校があれば、そちらに通うという選択肢もあります。
ただし、月曜日に保護者が学校に送迎して金曜日に保護者が学校まで迎えにいくようになります。また、平日に自宅以外で子どもが寝泊まりするようになるなど、生活環境がガラッと変わります。
あまりにも遠方にしか特別支援学校がない場合には、小学校の特別支援学級も選択肢に入る場合があると思います。
その場合は、特別支援学校に通うことが現実的に難しいことを踏まえ、小学校の特別支援学級の中で過ごせるよう学校に支援体制を求めていく必要が出てきます。
子どもや親の希望を尊重する
子どもの気持ちや、親の願いも重要です。
見学にはお子さんも連れて行き、本人の様子を観察したり意思表示できる場合には耳を傾けることも大切です。
実際に、パトまめの周りであったケースを紹介します。
保護者は地域の友達と一緒に学ばせたいという願いがありました。
しかしながら、お子さんを小学校と特別支援学校の見学に連れて行ったところ「特別支援学校に行きたい」とお子さん自身が意思表示をして、お子さんの気持ちを尊重して特別支援学校を希望したというケースがありました。
また、重度知的障害であるけれど、他の子どもを見て真似するのが好き・得意である子の親御さんは、小学校の特別支援学級に入った方ができることが増えるのではないかという願いを持って小学校の特別支援学級を選択したケースもありました。
結局学校に行くのは子ども本人ですし、子どものことを一番知り、将来こうなってほしいという願いを持っているのは親です。
なので、子どもや親の願い・希望がどうであるかをしっかりと考えて選択することもとても大切なことだと言えます。

ぼんちょの場合は、意思表示が難しいので、ぼんちょの障害の程度や支援ニーズを整理した上で、親の希望で特別支援学校を希望しました。
特別支援学校と小学校を実際に見学して比較する
学校説明会や見学の機会を活用して、実際の環境を見学することが大切です。
子どもが、その学校で快適に過ごせるかどうか、イメージできるのはどちらか?と検討するには、実際に足を運んでみるのが一番わかるかもしれません。
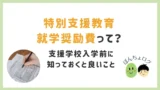
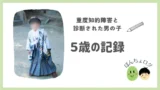
まとめ
重度知的障害の子の就学について、特別支援学校に就学するのと小学校に就学するのとでどのような違いがあるかやそれぞれのメリットとデメリットについてブログにまとめました。
そもそも就学先は完全に自由に親子が選べるわけではなく、発達検査等の資料を提出した上で最終的に適した就学先を判定されて決定します。
ですが、支援学校に通える就学判定が出されたとしても、お子さんの特性や子ども本人や親が何を望むかによっては、小学校の知的支援学級も検討できます。
最終的には、主治医や在籍する園の先生、療育を受けている児童発達支援のスタッフなどや学校関係者と相談しながら、その時に一番ベターだと思える選択をすることが大切です。
障害児の就学先の選択は親がとても悩むことの1つだと思いますが、ここでお子さんと向き合って悩んで考えたことやお子さんを理解しようとしたことは必ずプラスになります。
これから学校選びを進める同じ境遇の方がいらっしゃいましたら、皆さんにとって本記事が少しでも参考になれば幸いです。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!