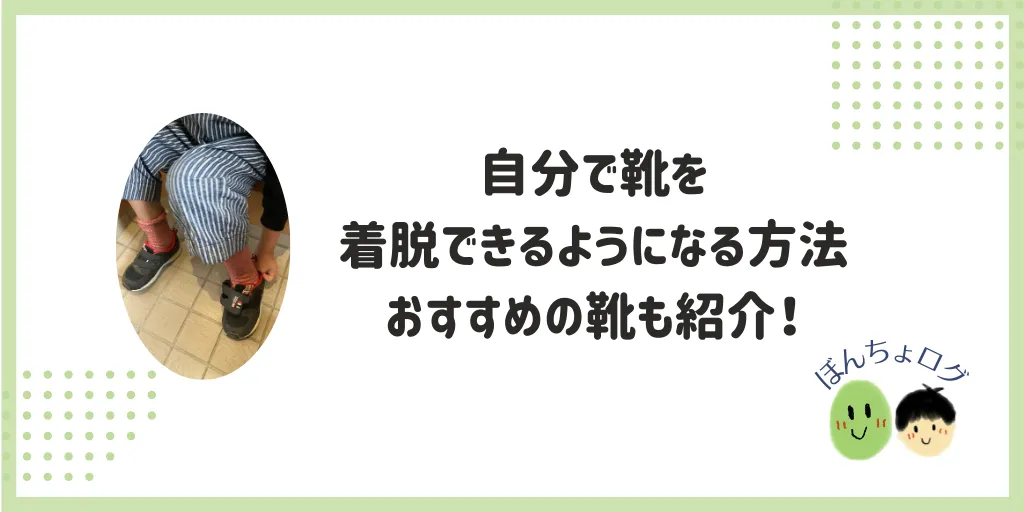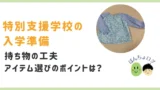身辺自立の中でも靴の着脱は最初に取り組みやすいことだと思います!
でも意外と重度知的障害のぼんちょは自分で靴が履けないし脱げないしで悪戦苦闘・・・(いや、悪戦苦闘したのは周りの大人かもしれない)

ぼんちょは2歳から靴の着脱に取り組んでいますが、なんと最終的に自分からやるようになったな〜と感じられたのは7歳です・・・。
今回は、重度知的障害のぼんちょの経験をもとに、自分で靴の脱ぎ履きができるようになるまでの環境設定のポイントや練習方法を紹介します。
それでは、靴の着脱ができるようになるまでの大事なポイントを見ていきましょう。
知的障害や発達障害の子が靴を着脱するためにはこれが必要!

知的障害や発達障害の子ども(だけでなくどの子にとっても)が靴を脱ぎ履きするために必要なことは、3つあります。
- 指でつまめたり足を上げたりなど身体的に靴を履ける段階まで育っていること
- 本人にとって脱ぎ履きしやすい靴であること
- 本人にとって靴の着脱に集中できる環境であること
靴の着脱ができるようになるには、この3つの条件が必要です。
もしもお子さんが、身体的に靴を履ける段階まできていない場合は、成長を待つか作業療法や療育で手先や足を使う訓練が必要になってきます。
今回は、身体的に靴を履ける段階にはあるけれど、靴の着脱がうまくいかない場合に焦点を当てて説明していきます。
靴の着脱がうまくいかない時に考えてほしいこと3つ
靴の着脱が上手くいかない理由としては、
- 本人にとって脱ぎ履きしづらい靴である
- 靴の着脱に集中できない環境である
- 手順の理解が難しい
といった理由が考えられます。
これらの理由から、お子さんがなかなか靴を自分で履いたり脱いだりできない時に考えてほしいことが3つあります。
順番に説明します。
着脱しやすいのはどんな靴?:おすすめの靴とアイテムも紹介
靴の着脱を練習する前に、本人にとって着脱しやすい靴を用意する必要があります。
本人にとって履きやすい靴は次のような靴です。
- サイズが合っている
- 足を入れる部分がガバッと開く
- マジックテープ
- 靴の後ろにタブが付いている
子どもの足のサイズの測り方についてはこちらのページが参考になりますので見てみてくださいね。
足のサイズ測定の用紙を自宅でダウンロードして使用することができます。
ですがじっとするのが難しいお子さんの場合、紙では測りにくいかもしれません。
その場合、最近ではダイソーにも20cmまで計れるフットメジャーが売られています。
家族みんなで使えるフットメジャーとしては、こちらがおすすめです。
「足を入れる部分がガバッと開く」
「マジックテープ」
これらは脱ぎ履きしやすい靴としての必要条件になります。
ぼんちょが色々試してみて一番おすすめできるスニーカーと上靴をご紹介します。
ぼんちょがずっと履いているムーンスターのキャロットは、程よく柔らかくてガバッと開きやすくてぼんちょも脱ぎ履きしやすそうです。
上靴も色々試しましたが、ムーンスターのこちらのタイプで脱ぎ履きできるようになりました。
上靴ってなんとなく硬くて履きにくいイメージがあるのですが、こちらの上靴は本当にガバッと開くしぼんちょが脱ぎ履きしてるのを見てもやりやすそうです。
これらの靴の後ろにはタグがついています。
なぜタグがついている靴がおすすめかというと、履く時に引っ張りやすいからです。
通っている園によっては、このタグにさらに「紐」や「リング」をつけるように言われます。
最近はダイソーにもこんなリングが売られています。

こちら、パンダの部分は色んなバージョンがあるのですが、はっきり言うと不器用なお子さんに最初に使うリングとしてはこちらの商品はおすすめしません。(でも履くのが上手くなってきた時にリングを外す前の段階として使うなら可愛いしおすすめ!)
ぼんちょも最初使用していましたが、リングが小さすぎてつまみにくく、足と一緒に靴の中に入ってしまってかえって履きにくくなりました・・・
そこで、ぼんちょの靴にはこちらを付けました!

こちらもダイソーで入手したプラスチックのリングです。
こちらはリングに手がいきやすく、靴を履く助けになっていると実感できます。
もしリングをつけることを検討される場合は参考にしてみてくださいね。
もしお子さんが特別支援学校に入学予定で、他にも学校の持ち物の工夫が知りたい場合はこちらの記事がおすすめです↓
靴を着脱しやすいのはどんな環境?:場所やタイミング
靴の着脱を練習する前に、本人にとって集中できる環境を用意することが大事です。
本人にとって靴の着脱に取り組みやすい環境を探るときに考えることリストにしてみます。
- 視覚的・聴覚的に気が散るものがないか
- 「椅子に座って」or「床に座って」ではどちらが着脱しやすいか
- 前の活動から靴を履くモードに切り替わっているかどうか
ぼんちょの場合は次の環境が靴の脱ぎ履きに適していました。
- 外よりも室内
- 床や低い段差に座っての方が着脱しやすい
- 次に楽しみな活動が設定してある
ぼんちょの場合、靴の着脱ができない一番の要因は気が散って靴がまったく目に入らないことでした。
ずっと外の靴箱の横に座って練習していましたが、なかなか靴を履くことに集中できません。
小学生になって通うようになった放課後等デイサービスでは、室内に設定してあるプレイエリアに入る時には上靴を脱ぐ必要がありました。
すると、なんと靴に注目できなかったぼんちょが自分から上靴を脱ぐように!
そしてプレイエリアから出て上靴を履く時も、自分から足を入れようとするようになりました。
ぼんちょにとっては外よりも室内の方が気が散らずに集中でき、着脱の練習に向いてることがわかりました。
また、椅子に座るとしっかり前に屈まないと手が届きませんが、ぼんちょの場合は床に座れば手が届きやすくて靴を脱ぎやすいことが判明しました。
そして、靴の着脱の後には「プレイエリアで遊べる」「移動してどこかに行ける」「外に出られる」など本人にとって好きな活動があると、そのために靴の着脱を頑張れます。
そこで、本人にとって楽しみな活動の前に靴の着脱を頑張る時間を設定して回数を重ねることで靴の着脱ができるようになっていきました。
このように、自分で靴の着脱ができるようになるまでには、本人にとって一番靴の着脱に集中しやすい場所や自然に着脱したくなるタイミングを考えることがとても大事です。
手順を小分けにしてスモールステップで練習
それぞれの手順をわかりやすくしてスモールステップで練習していくことで靴の着脱ができるようになっていきます。
靴を履く手順を表してみます。
- 座る
- 靴を持つ
- マジックテープを剥がす
- 足の入り口を広げる
- つま先を入れる
- 靴の後ろのタブやリングを持つ
- かかとをぐっと押し入れる
- マジックテープを貼る
小分けに書くとこんなにもすることがあるのです。
スモールステップで挑戦する場合、できそうな部分から挑戦します。
ぼんちょの場合は、最初のマジックテープを剥がすところから足の入り口を広げるまでは補助しました。

まずはつま先を入れたらOKにしました。
そこからその後のかかとを入れる・マジックテープを貼るところまでが先にできるようになりました。
このように、スモールステップで取り組むときは手順の最初から頑張るのではなく、できそうなところから順番に「できた」を積み重ねていくのが鉄則です。
次に脱ぐ手順です。
- 座る
- マジックテープを剥がす
- かかとを持つ
- 靴から足を抜く
丁寧に書くとこの手順です。
ですが、実際にぼんちょがどうかというと、
座った後に
マジックテープは剥がさずかかとを持って足を抜く
ですね。
脱ぐという目標は達成できているのでこれで良しとしています。

「履く」時もマジックテープを剥がさずに履くことがよくあります・・・
ちなみに靴を「履く」と「脱ぐ」。
どちらから取り組むべきでしょう?
手順を見たら一目瞭然、「脱ぐ」の方が操作的にはハードルが低いのです。
でも、ぼんちょの場合は、最初脱ぐ方が意識しづらかったです

外靴を脱がずに足を上げて上靴を履こうとしていて「あれれ・・・?」という感じでした。
なので、ぼんちょの場合は靴の着脱全体で見た時には一番最初にできるようになったことは「履く」の中の「つま先を入れる」ことでした。
子どもによって、どこから取り組みやすいかも全然違いますのでお子さんに合った方法で練習してみてくださいね。
まとめ
今回は、知的障害や発達障害のお子さんが自分で靴の着脱ができるようになるための方法を紹介しました。
靴を脱ぎ履きできるようにするために本人に合った靴や環境を用意する必要があります。
また練習するタイミングも、本人が頑張れるタイミングを見つけましょう。
靴の着脱の手順を細かく分けて、お子さんが取り組みやすいところからスモールステップで「できた」を積み重ねることが大事です。
今回紹介した内容は、実際に重度知的障害と診断されているぼんちょとその家族の実際の経験をもとに作成しています。
過去の我が家と同じように、靴の着脱に取り組みたいけどなかなか取り組もうとしないお子さんがいるご家庭に少しでも参考になることがあれば幸いです。
もし、何かお気づきの点がありましたら、お問い合わせページよりお知らせください。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。