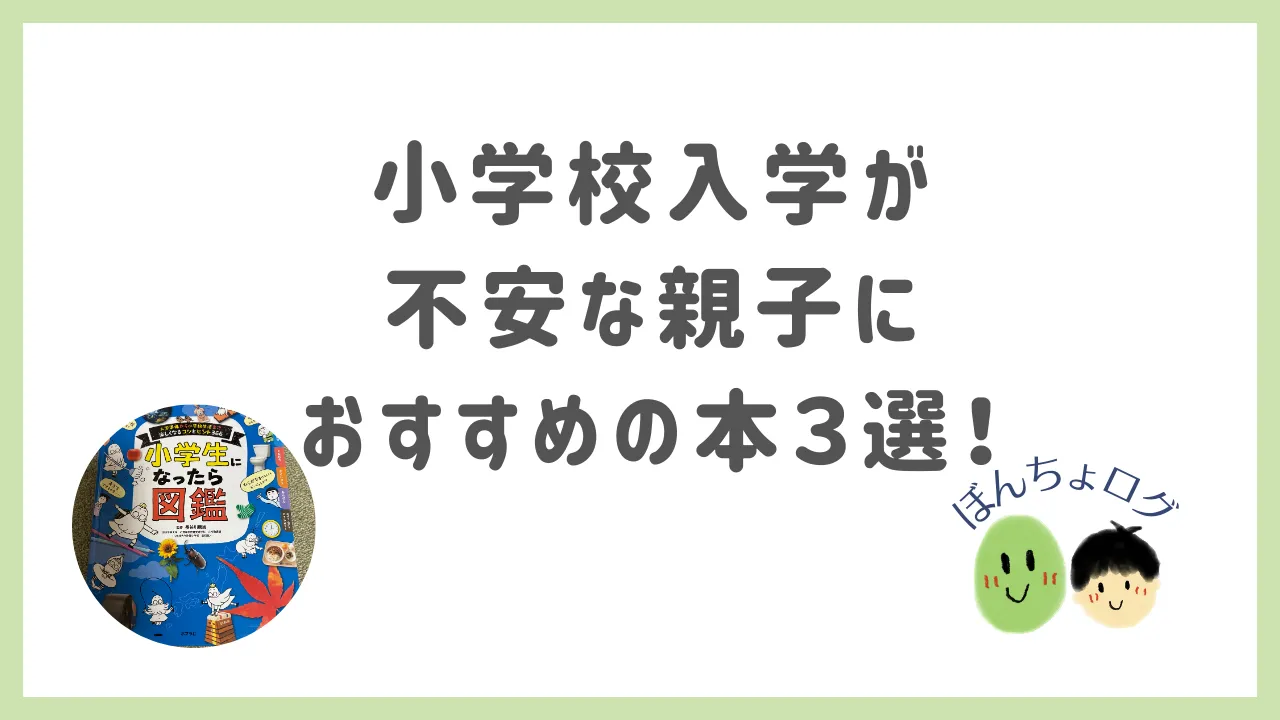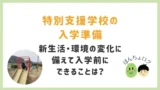重度知的障害児ぼんちょを育てているパトまめが小学校入学前に心配事があるお子さんやご家族におすすめな本をブログで紹介します。
今回は、特別支援学校に通う予定のお子さん向けというより地域の小学校に通う予定のお子さん向けの情報です。ですが、特別支援学校に通う予定のお子さんにとっても参考になる書籍も紹介しますので良かったらご覧ください。
近々小学校に入学する子がいるご家庭は、ドキドキですよね。
我が家は、小学校に入学した「ぼんちょ兄」と特別支援学校に入学した「ぼんちょ」とで2回の入学を経験しました。

子どもたちが年長の時は私もドキドキでしたよ!
今回はおもに「ぼんちょ兄」が小学校に入学するにあたって親子で小学校生活への不安を解消するのに利用して良かった本を紹介します。
障害の有無に関わらず、小学校入学は「楽しみ」な気持ちと「不安」が同居するもの。
「うまくやっていけるかな」
「心配だな」
そんな気持ちが少しでも心にあるならば、お子さんに障害があっても無くても是非この記事を読んでいただければ幸いです。
一番おすすめ!入学前に小学校生活を知る決定版「小学生になったら図鑑」
「小学生になったら図鑑」は入学前後に子どもに伝えたい情報が網羅されている
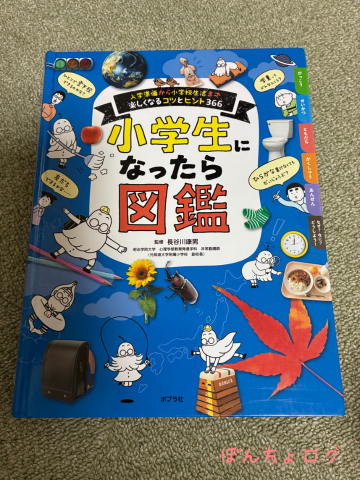
「小学生になったら図鑑」という書籍名からしてワクワクしますよね。今回他にも紹介しますが、ぶっちゃけ言います。

この本1冊がすベてを網羅しています。
↓新訂版が出ているので今から買うならこちらの緑色の表紙がおすすめ
自信を持っておすすめできる良本です。
- フルカラー写真で登校から下校までの「1ねんせいの1にち」が紹介されている
- 「生活」や「友達」について知っておいた方が良いこと満載
- 親が読むと小学生に必要なスキルがわかる
「小学生になったら図鑑」は「図鑑」というだけあって写真・イラストが非常に多い特徴があります。
なので文字がまだ読めなくても理解しやすいですし、イメージがつかみやすいです。
写真多めなので、写真で理解できるお子さんの場合は支援学校に行く子にもおすすめできます。
ちなみに文字は全てふりがな付きで全体的に文量が少ないです。
小学校生活について、次のようなことがわかります。
教室の様子
ランドセルやお道具箱の中身
教科で何を勉強するのか
休み時間の選択肢
入学式の様子 ・・・etc

網羅されすぎててすごくないですか?!
それだけでなく、「服のたたみ方」「ひもの結び方」「ぞうきん掃除の仕方」「うわばきの洗い方」までイラスト・写真つきで手順が載っています。つまり
入学後もかなり使えます。入学前も。
そのほか「友達の家で過ごす時のマナー」や「鍵の扱い方」まで・・・網羅しすぎててちょっと怖いくらいです。
「小学生になったら図鑑」に代わる絵本「1ねん1くみの1にち」とは?
「小学生になったら図鑑」の難点は・・・しいて言うなら重いこと?
持ち運ぶのにはあまり適しません。
軽いのが良い
持ち運びたい
とりあえず小学校の雰囲気だけ伝えたい
という人には「1ねん1くみの1にち」という絵本もおすすめです。
「小学校になったら図鑑」冒頭にある「1ねんせいの1にち」と似た内容なので、良かったら手に取ってみてください。
社会的に適した行動を理解するためのヒント集「ソーシャルストーリーブック」
「ソーシャルストーリーブック」は社会で起きることや場面を理解するのに役立つ本
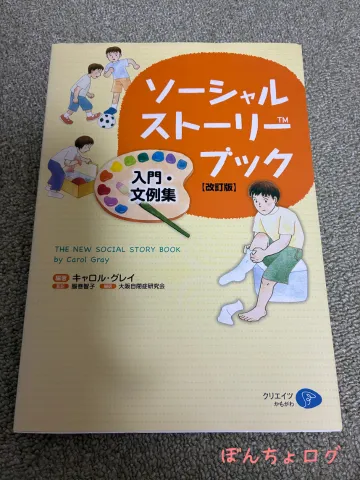
「ソーシャルストーリーブック」は、ほとんどが文字。
先ほど紹介した図鑑とは180度ちがう形式です。
- 社会から取り出した場面や状況について短い文を使って説明していてわかりやすい
- 子どもが不安に感じていることを親として説明する参考になる
「怖い」「不安」でパニックになる
マナーやルールが守れない
空気が読めない・暗黙の了解がわからない
知的障害がある場合は知能の問題でこのような困り事が起こる場合もあります。
ですが、知的障害でないとしても、これらの困り事は起こりえます。

親としては、なんとかしたいですよね。
「学校生活、大丈夫かな?」と心配になる人もいるかもしれません。
これらの困りごとの理由は次のことが考えられます。
起きている事象・状況を自分だけの力で正しく理解できない
経験がなくてわからない
想像するのが苦手
障害がなくとも、未就学のお子さんはだいたいこんな感じでもおかしくはないですよね。
ですが、小学生前後のお子さんがこのような特性を理由に、とても困っている場合は、「ソーシャルストーリーブック」が役立つかもしれません。
「ソーシャルストーリーブック」を実際に使用した事例
実はぼんちょ兄は幼稚園の頃、「避難訓練」が大嫌いでした。大きい音が鳴るのが特に嫌だったそうです(本人談)。
その時に出会ったのが「ソーシャルストーリーブック」。
この本の中に「『かさいけいほう』がなったとき」という項目があります。
ここからヒントを得て次のようなソーシャルストーリーを作りました。
ようちえんで「けいほう」がなることがあります。
みんなにきこえるために、おおきいおとがなります。
「けいほう」がなるのは、「ひなんくんれん」のあいずです。
「ひなんくんれん」は、ほんとうにかじになったときのためのれんしゅうです。
たいていは、けいほうがなっても、ほんとうのかじではありません。
せんせいは、ぼくがクラスのみんなとあつまるのをまってくれます。
だいじなのは、みんなといっしょにしずかにあるくことです。
ぼくはおちついてあるいてそとにでます。
せんせいが「ひなんくんれんはおわりです」というまでそとでまちます。
「ひなんくんれん」がおわったら、せんせいがつぎにすることをおしえてくれます。
「ソーシャルストーリーブック(改訂版)」(キャロルグレイ編著/クリエイツかもがわ)を参考に作成
ソーシャルストーリーを一緒に読むことで、幼児だったぼんちょ兄は避難訓練について次のことを理解することができました。
・避難訓練は本当に火事になった時のために必要な練習であること
・突然大きな音が鳴るのは、みんなに聞こえるためであること
すると、
「大きい音は苦手だけど小さい音だとみんなに聞こえないから仕方ない」
「練習はやっておいた方が良い」
「好きではないけど必ず終わる」
こんな風に納得できるようになったのです。
避難訓練があるとわかっても「幼稚園に行かない」と言うことは無くなりました。

ソーシャルストーリーは、「ことば」で説明するため、本人合わせてわかる言葉で短い文を組み合わせて作るのがコツです。
お子さんが初めてのことに直面する時、わからないことがある時に、ソーシャルストーリーを作ってお子さんに説明することは、お子さんの理解を助ける1つの方法になるはずです。
書籍には、多くの例文が載っていて参考になります。
良かったら、小学校生活に向けて一度手に取ってみてください。
小学校に行き始めるとどんなことに困るのか予測するのに役立つ「こんなとき、どうする?発達障害のある子への支援」
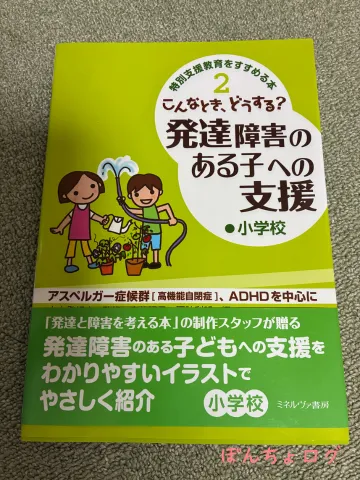
「こんなとき、どうする?発達障害のある子への支援・小学校」は、小学校の先生向けの書籍です。
- 小学校で起こりそうなトラブルを我が子に当てはめて想像できる
- 小学校で対応してもらえるかもしれない方法を知ることができる
「こんなとき、どうする?発達障害のある子への支援・小学校」には、トラブル事例が14例掲載されています。その事例ごとに次の順序で手立てが書かれています。
その場ですぐできる対応
その場でしてはいけないNG対応
その子に合わせた支援プランのアイデア(環境調整など)
事例を知ることは、家族として小学校生活に向けて心配なことを整理するのに役立ちます。

事例ごとに「その場でしてはいけないNG対応」も載っていて、家庭でもやってしまっていないか振り返ることができますよ!
ただし、この本で保護者として知識をえたとしてもやめた方が良いのは、学校の先生に「してもらいたい支援」を押し付けることです。
学校の先生は、子ども本人やクラス環境に合わせて対応してくださいます。
また、お子さんの様子が家庭と学校とでは違うこともあります。
なので、家族が「こうすべきだ」と一方的に学校の先生に言っていくのは最善ではありません。

ですが、家族として次のことを伝えておくのは大切!
「どんな子どもであるか」
「苦手な場面」
入学時は、先生もどんな子どもであるかの情報がほとんどありません。
子どもの特性や特徴がわかっていると近道で良い支援にたどりつける可能性は高まります
「こうしてほしい」ではなく「こういう特徴のある子なので、家庭や園ではこのように対応してきました」など、あくまで情報提供という形で懇談等で伝えておくのは良い方法です。
「こんなとき、どうする?発達障害のある子への支援・小学校」を読むことで家族として小学校生活に向けて心配なことを整理することができます。
先に学校に伝えておいた方が良さそうな子どもの情報を整理するためにも、この本を手に取るのはおすすめです。
ちなみに「幼稚園、保育園編」と「中学校編」もあります。
↓小学校入学後に気をつけたいトラブルの話
まとめ
今回はおもに小学校に入学するにあたって親子で小学校生活への不安を解消するのに利用して良かった本3冊を紹介しました。
まずは小学校生活を知るために、小学校生活がわかる写真が載っている書籍(=小学生になったら図鑑)を親子で活用することをおすすめします。
子ども本人にとって不安なことを減らす手立てとして、「ソーシャルストーリーブック」
親にとって気がかりなことを準備する手立てとして、「こんなとき、どうする?発達障害のある子への支援・小学校」を紹介しました。
ご家庭の環境やお子さんの特性はそれぞれ違います。なので、今回紹介した書籍が必ず当てはまるご家庭ばかりではないことをご了承ください。
よかったらXでも気軽にフォローしてください。
最後まで読んでくださりありがとうございました!
↓支援学校入学に向けて、環境の変化に備えて準備したことはこちらから
↓就学選択についての記事はこちらから